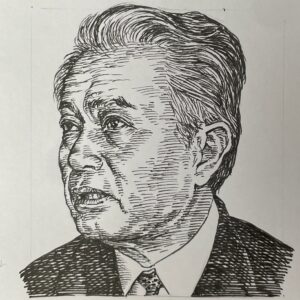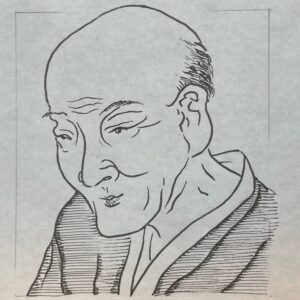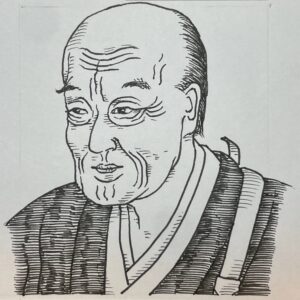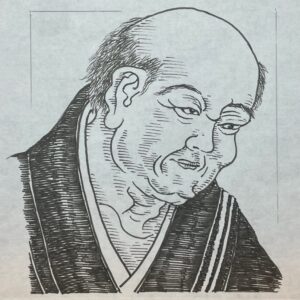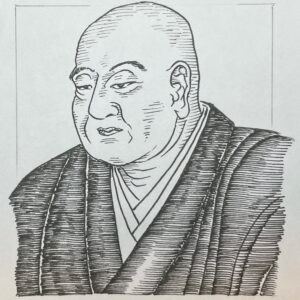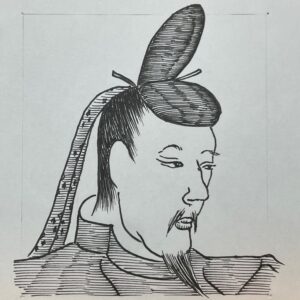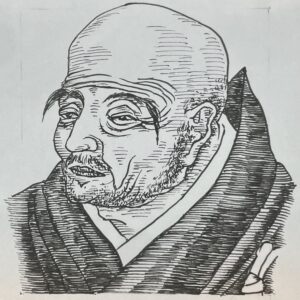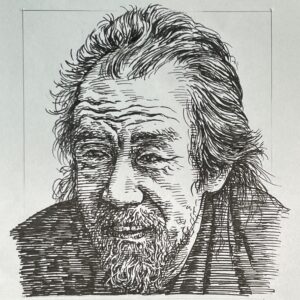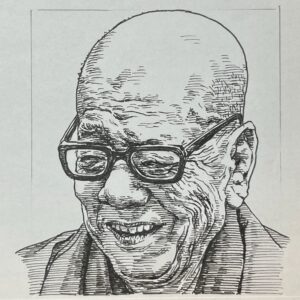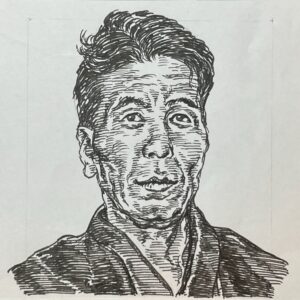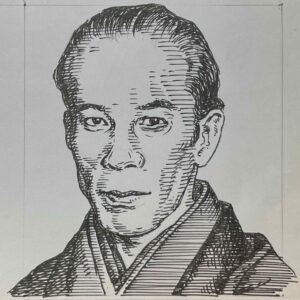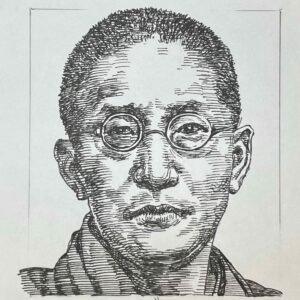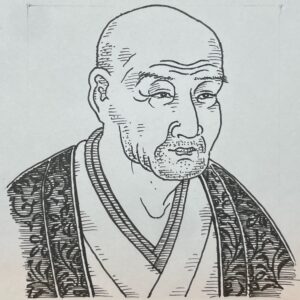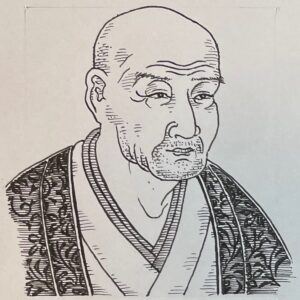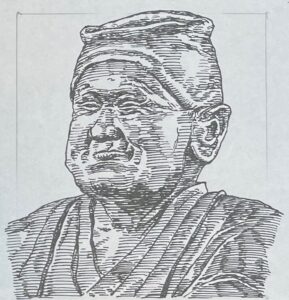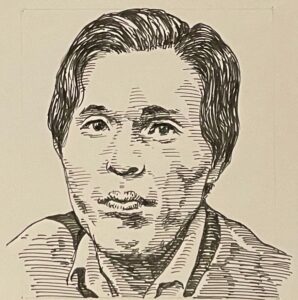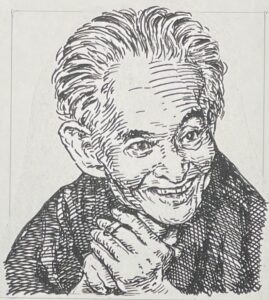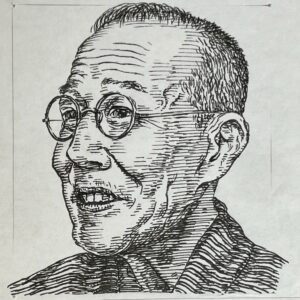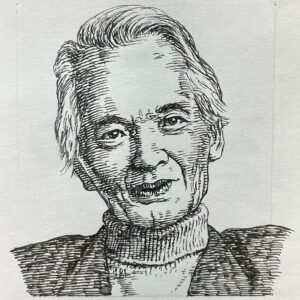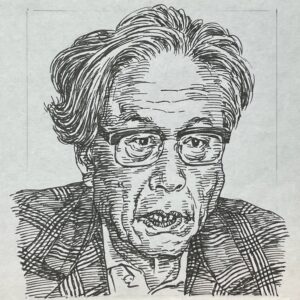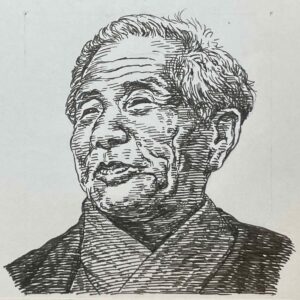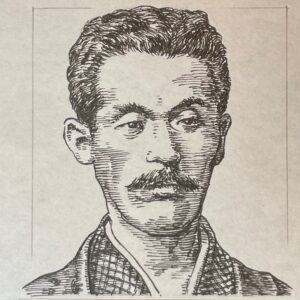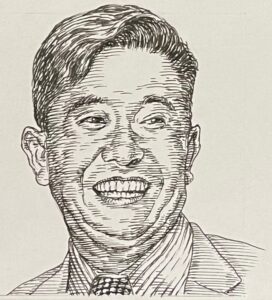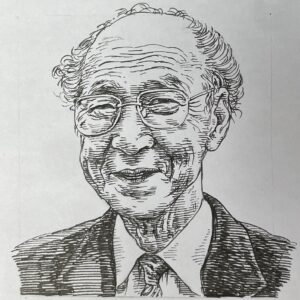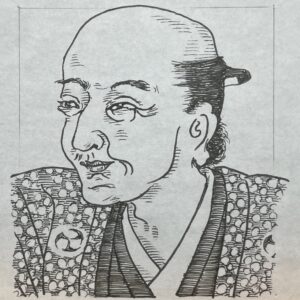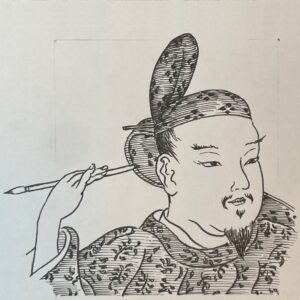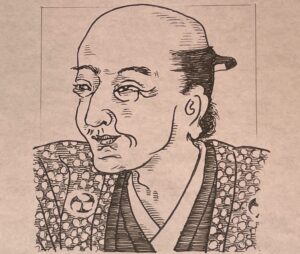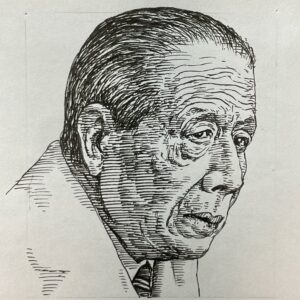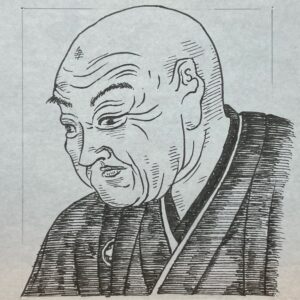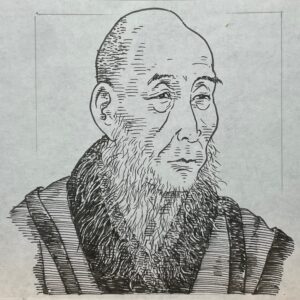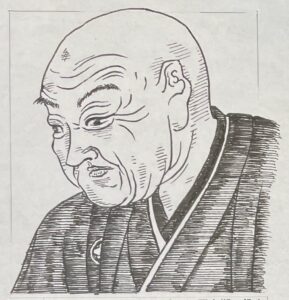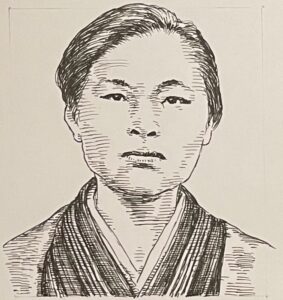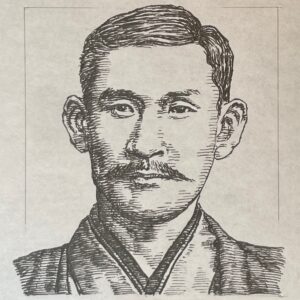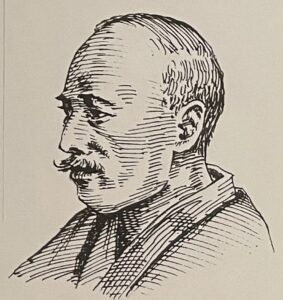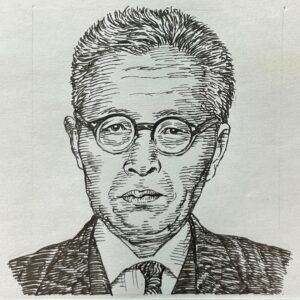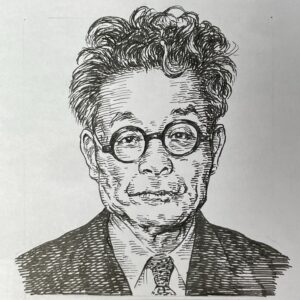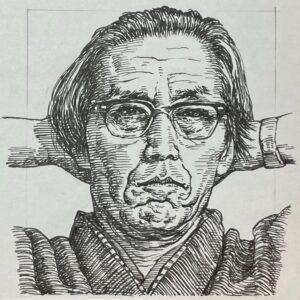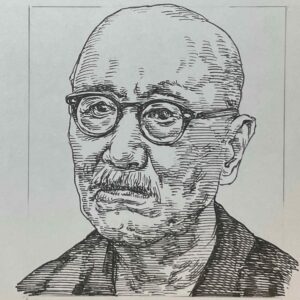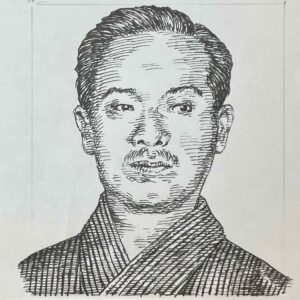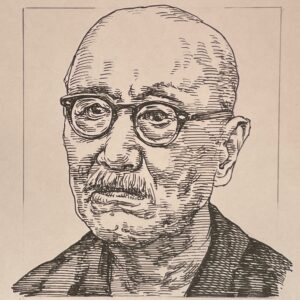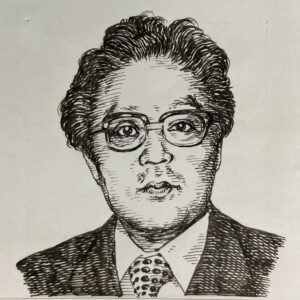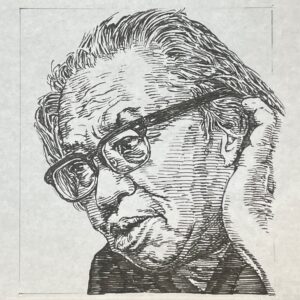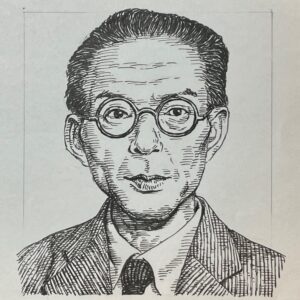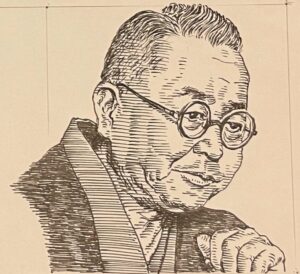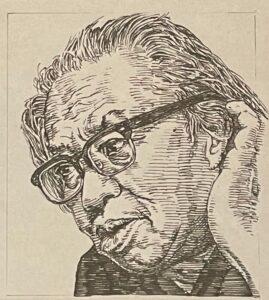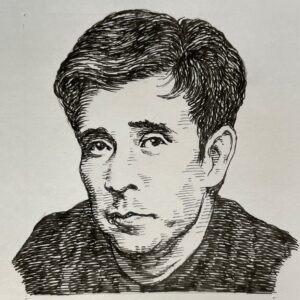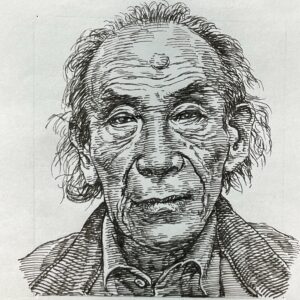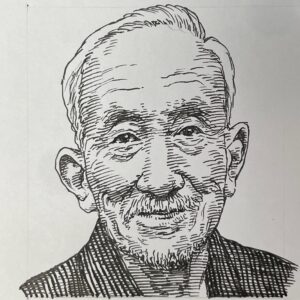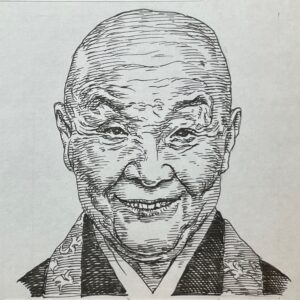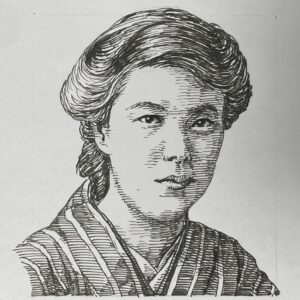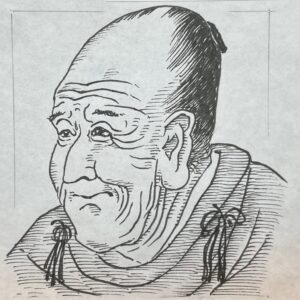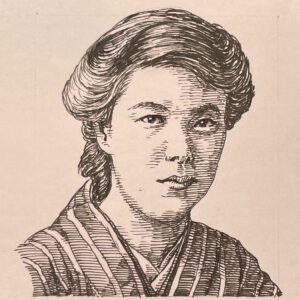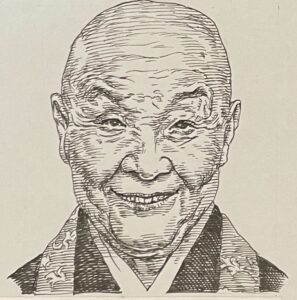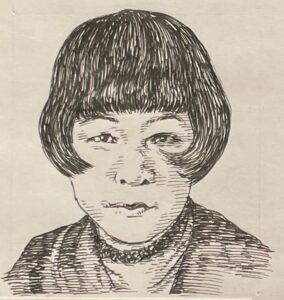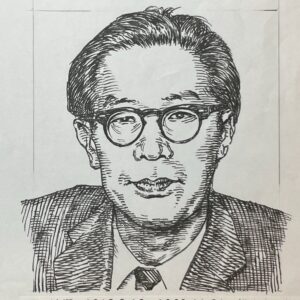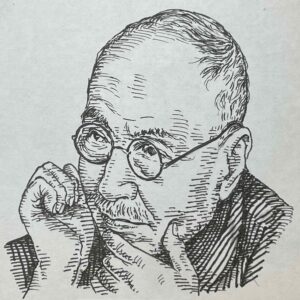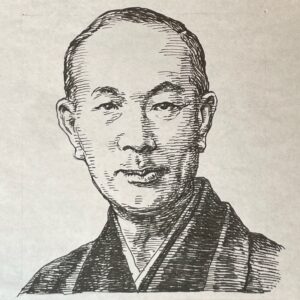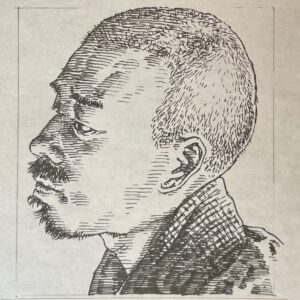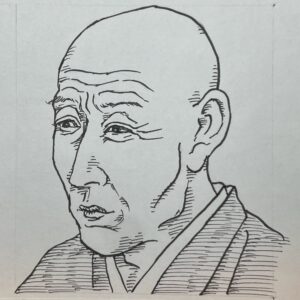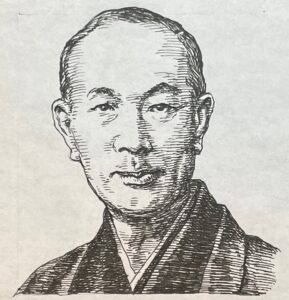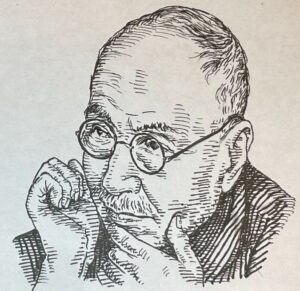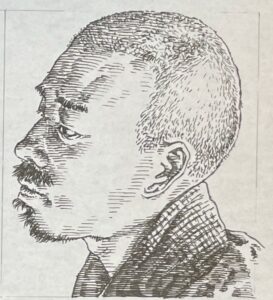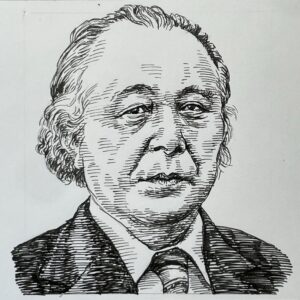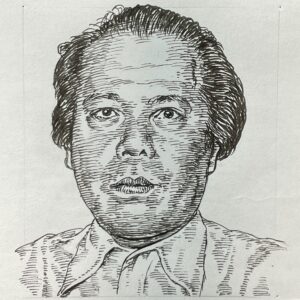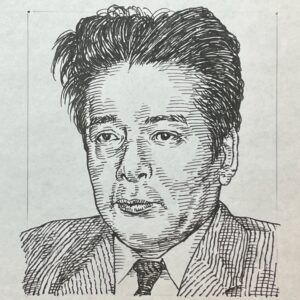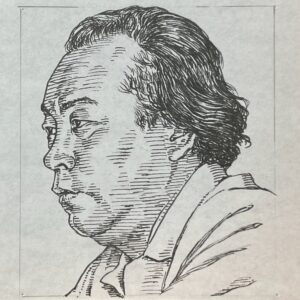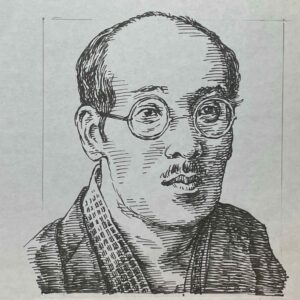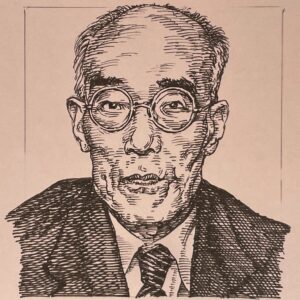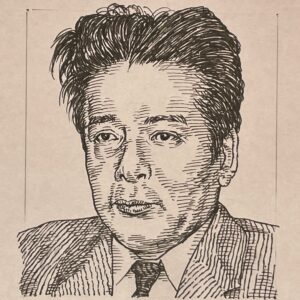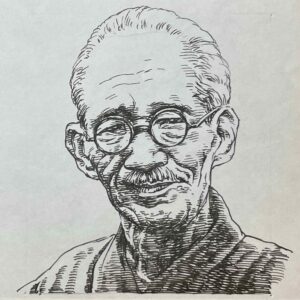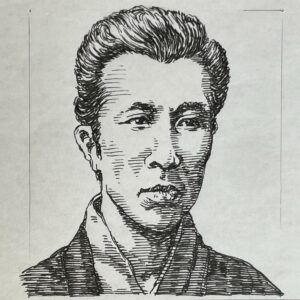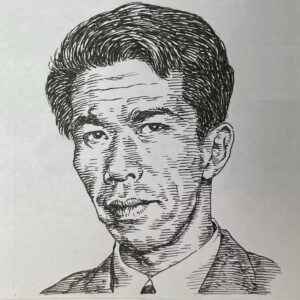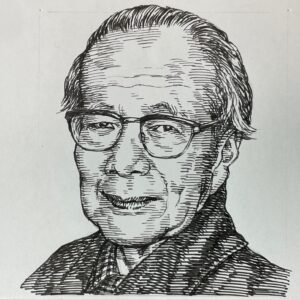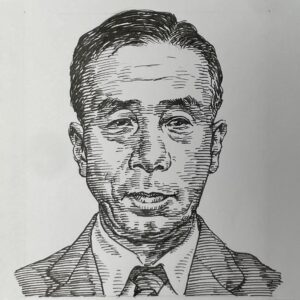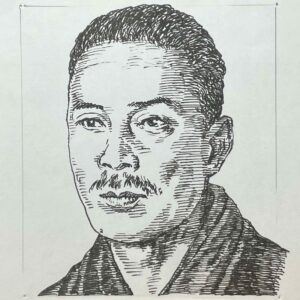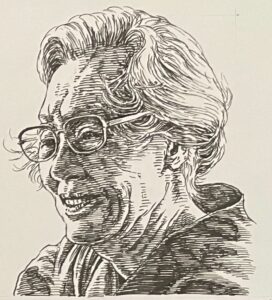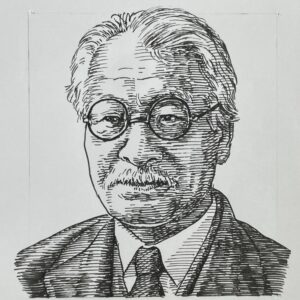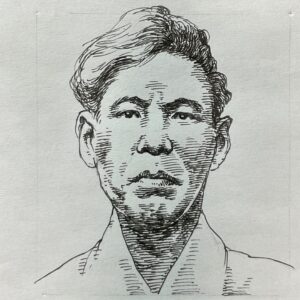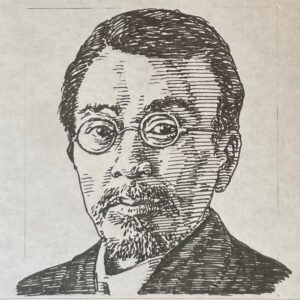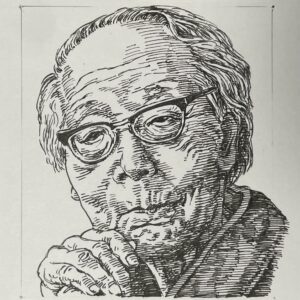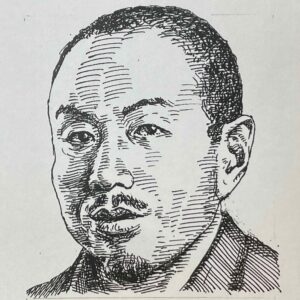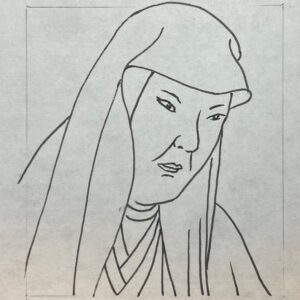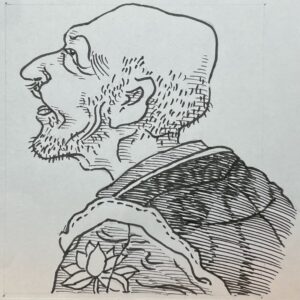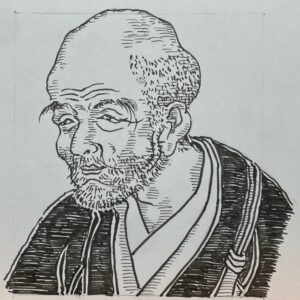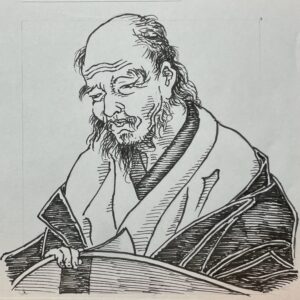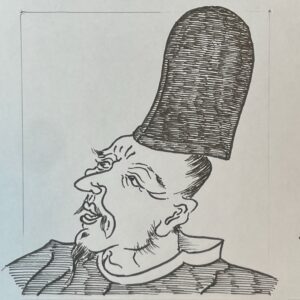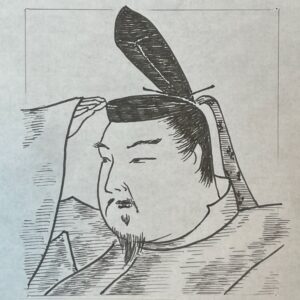文学
Literature
ようこそ!フリーイラストポートレートと
歴史の停車場いらすとすてーしょんへ
こちらのページでは、Syusuke Gallery
に展示しております文学者イラストポートレートをご覧いただけます
どうぞ文学の部屋をお楽しみください
目次
- 1. It's New 文学の部屋
- 2. 文学者イラストポートレート Syusuke Galleryより
- 2.1. 世界の文学家
- 2.1.1. アメリカ合衆国United States of America
- 2.1.2. ドイツ連邦共和国Federal Republic of Germany
- 2.2. 日本の文学家
- 2.2.1. 北海道Hokkaido
- 2.2.2. 青森県Aomori
- 2.2.3. 岩手県Iwate
- 2.2.4. 宮城県Miyagi
- 2.2.5. 秋田県Akita
- 2.2.6. 山形県Yamagata
- 2.2.7. 福島県Fukushima
- 2.2.8. 茨城県Ibaraki
- 2.2.9. 栃木県Tochigi
- 2.2.10. 群馬県Gunma
- 2.2.11. 埼玉県Saitama
- 2.2.12. 千葉県Chiba
- 2.2.13. 東京都Tokyo
- 2.2.14. 神奈川県Kanagawa
- 2.2.15. 新潟県Niigata
- 2.2.16. 富山県Toyama
- 2.2.17. 石川県Ishikawa
- 2.2.18. 福井県Fukui
- 2.2.19. 山梨県Yamanashi
- 2.2.20. 長野県Nagano
- 2.2.21. 岐阜県Gifu
- 2.2.22. 静岡県Shizuoka
- 2.2.23. 愛知県Aichi
- 2.2.24. 三重県Mie
- 2.2.25. 滋賀県Shiga
- 2.2.26. 京都府Kyoto
- 2.2.27. 大阪府Osaka
- 2.2.28. 兵庫県Hyogo
- 2.2.29. 奈良県Nara
- 2.2.30. 和歌山県Wakayama
- 2.2.31. 鳥取県Tottori
- 2.2.32. 島根県Shimane
- 2.2.33. 岡山県Okayama
- 2.2.34. 広島県Hiroshima
- 2.2.35. 山口県Yamaguchi
- 2.2.36. 徳島県Tokushima
- 2.2.37. 香川県Kagawa
- 2.2.38. 愛媛県Ehime
- 2.2.39. 高知県Kochi
- 2.2.40. 福岡県Fukuoka
- 2.2.41. 佐賀県Saga
- 2.2.42. 長崎県Nagasaki
- 2.2.43. 熊本県Kumamoto
- 2.2.44. 大分県Oita
- 2.2.45. 宮崎県Miyazaki
- 2.2.46. 鹿児島県Kagoshima
- 2.2.47. 沖縄県Okinawa
- 2.2.48. 出生地不明Unknown
It's New 文学の部屋
文学者
イラストポートレート Syusuke Galleryより
出身国別、都道府県でお届けしています
世界の文学家
アメリカ合衆国
United States of America
ドイツ連邦共和国
Federal Republic of Germany
該当の投稿はありません。
日本の文学家
北海道
Hokkaido
青森県
Aomori
岩手県
Iwate
宮城県
Miyagi
秋田県
Akita
山形県
Yamagata
福島県
Fukushima
茨城県
Ibaraki
栃木県
Tochigi
群馬県
Gunma
埼玉県
Saitama
千葉県
Chiba
東京都
Tokyo
神奈川県
Kanagawa
新潟県
Niigata
富山県
Toyama
石川県
Ishikawa
福井県
Fukui
山梨県
Yamanashi
長野県
Nagano
岐阜県
Gifu
静岡県
Shizuoka
愛知県
Aichi
三重県
Mie
滋賀県
Shiga
京都府
Kyoto
大阪府
Osaka
兵庫県
Hyogo
奈良県
Nara
和歌山県
Wakayama
鳥取県
Tottori
島根県
Shimane
岡山県
Okayama
広島県
Hiroshima
山口県
Yamaguchi
徳島県
Tokushima
香川県
Kagawa
愛媛県
Ehime
高知県
Kochi
福岡県
Fukuoka
佐賀県
Saga
長崎県
Nagasaki
熊本県
Kumamoto
大分県
Oita
宮崎県
Miyazaki
鹿児島県
Kagoshima
沖縄県
Okinawa
該当の投稿はありません。
出生地不明
Unknown
いらすとすてーしょん検索コーナー
新着偉人(It's New)
新たに公開のイラストポートレートをご覧ください
【文学の部屋|山上路夫】昭和時代編.232New!!
2026-02-16
【文学の部屋|水島 哲】昭和時代編.231
2026-02-15
1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓
2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です
2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします
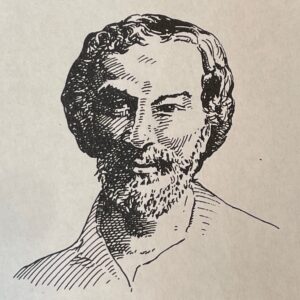


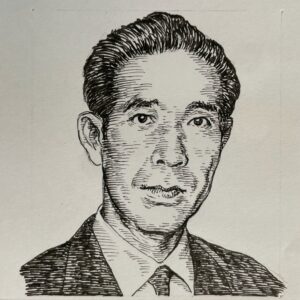


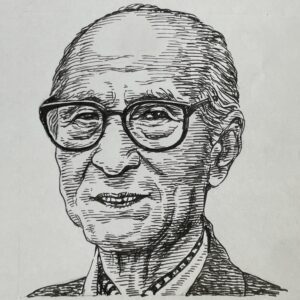



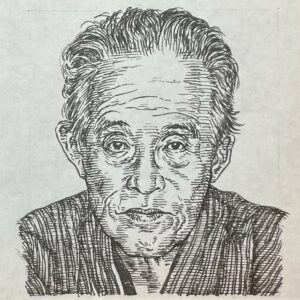








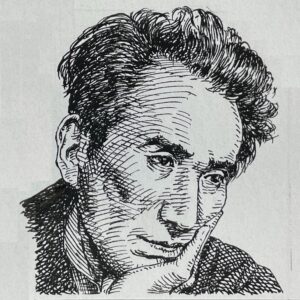

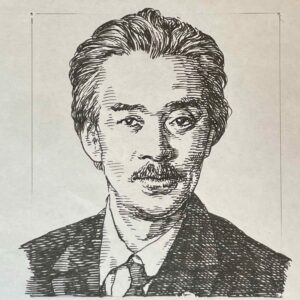

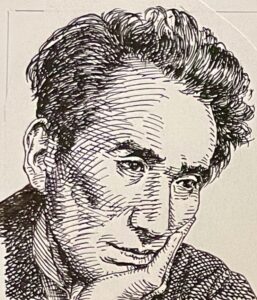


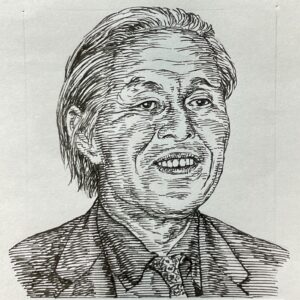
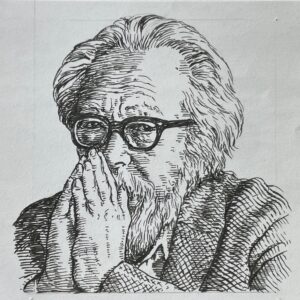

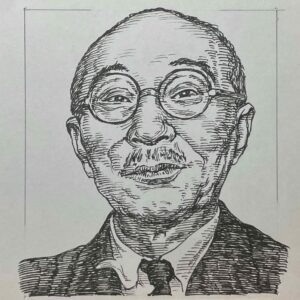


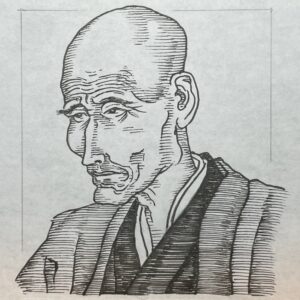
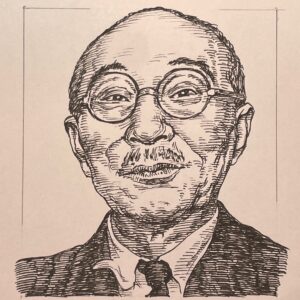
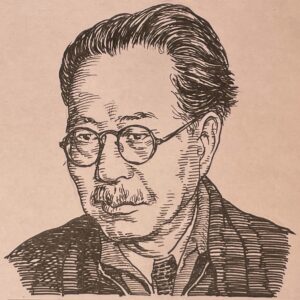



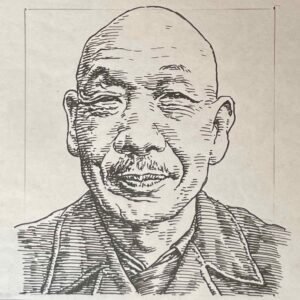
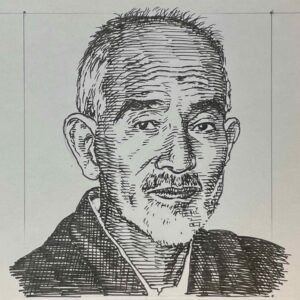
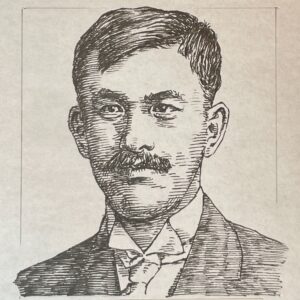
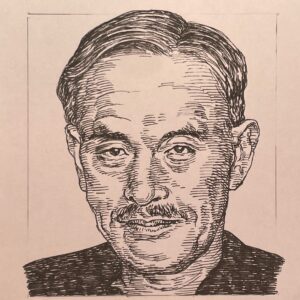
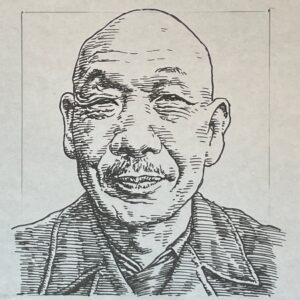




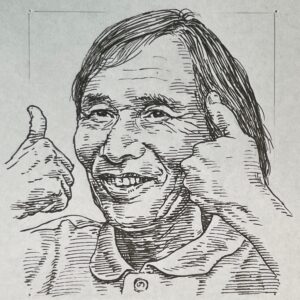

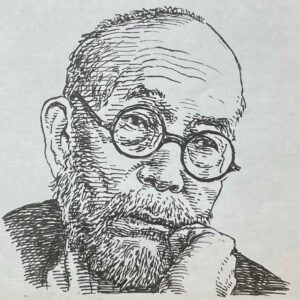

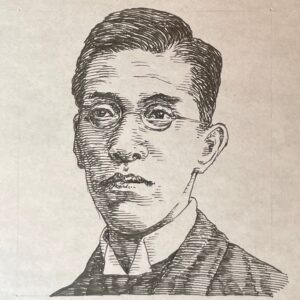
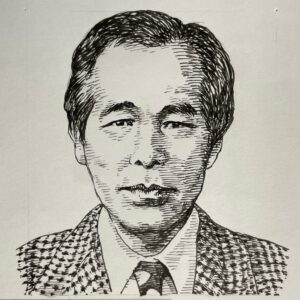
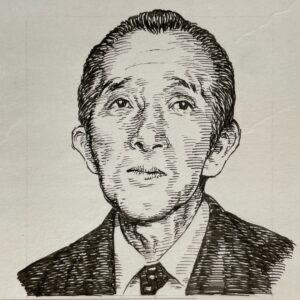

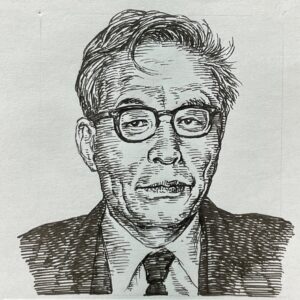




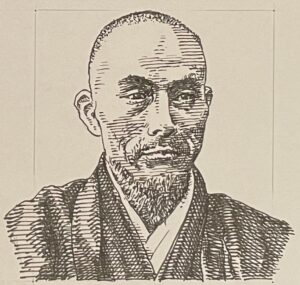

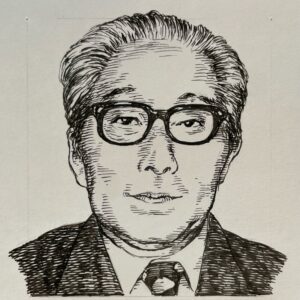

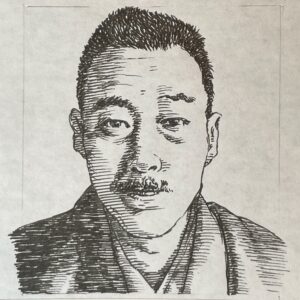
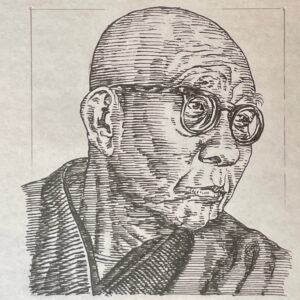

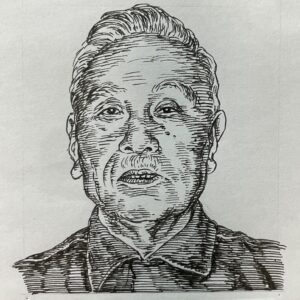

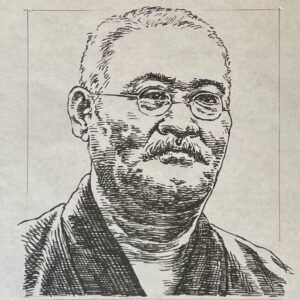
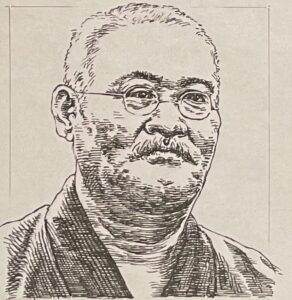


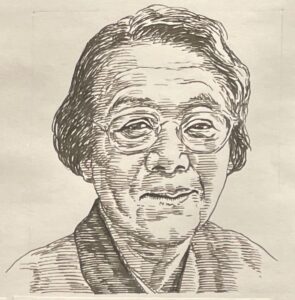

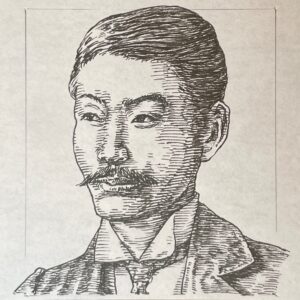

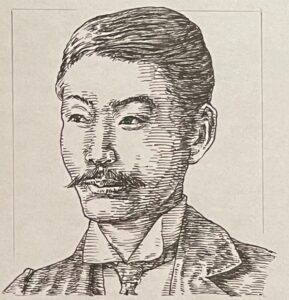
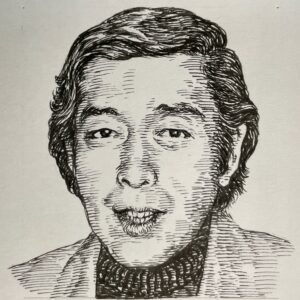
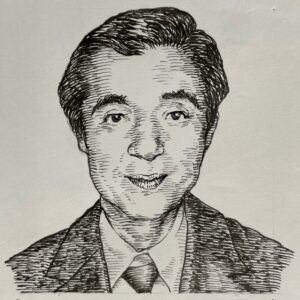

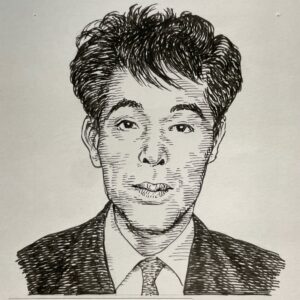
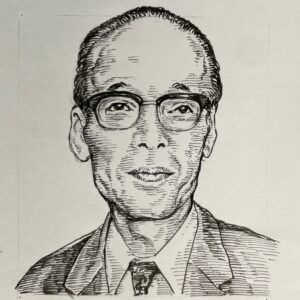

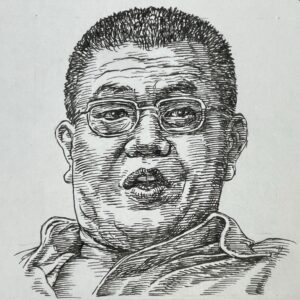

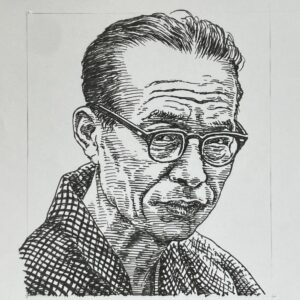
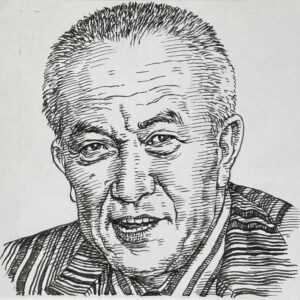
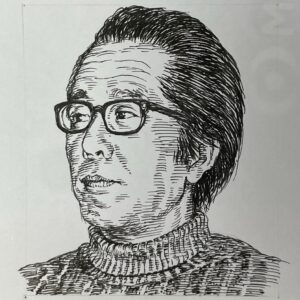
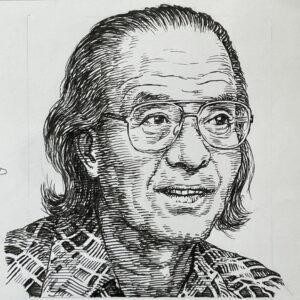
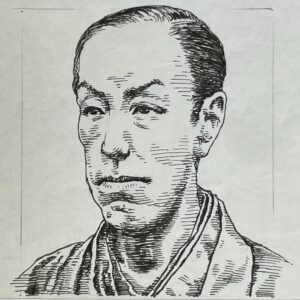
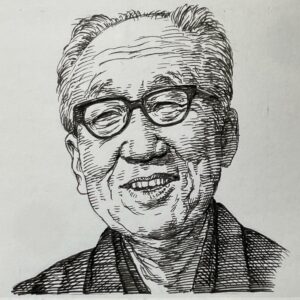
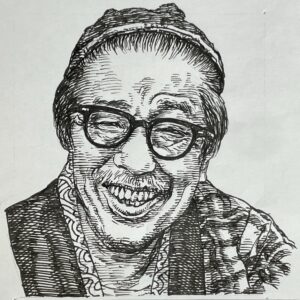





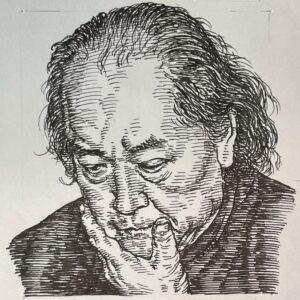




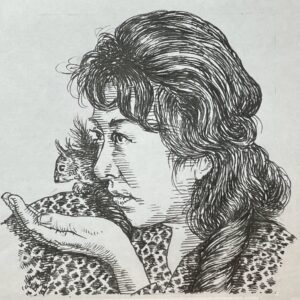


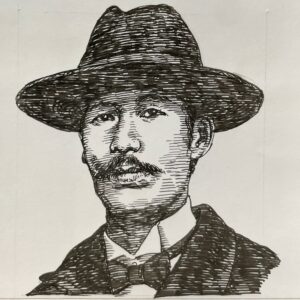


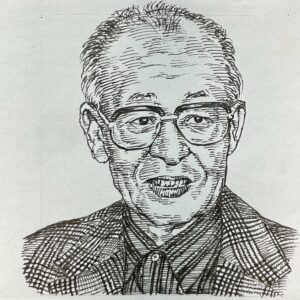
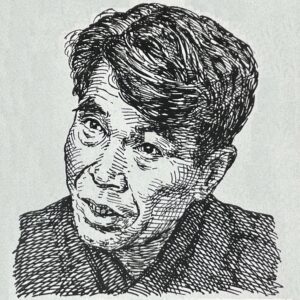

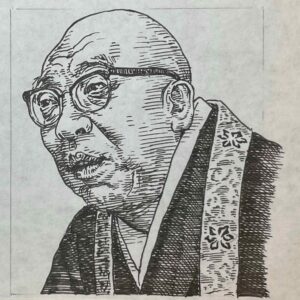


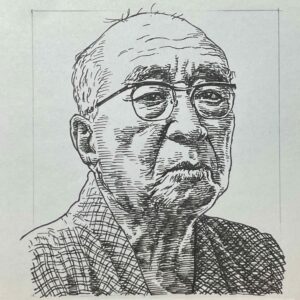
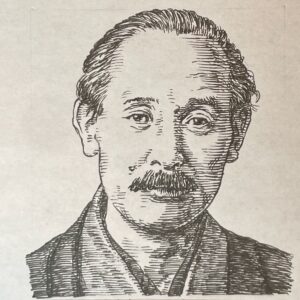





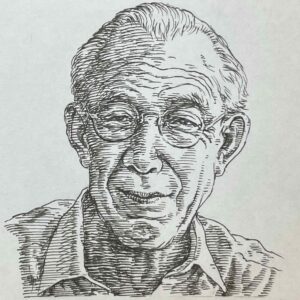
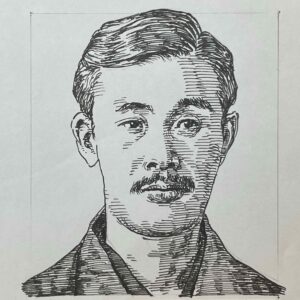

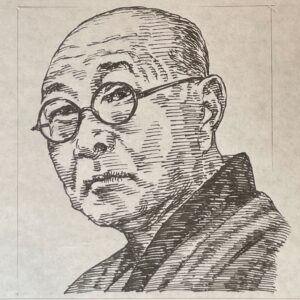


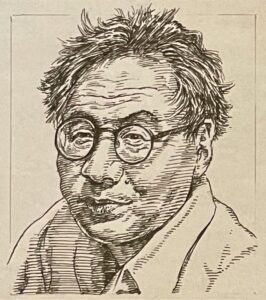
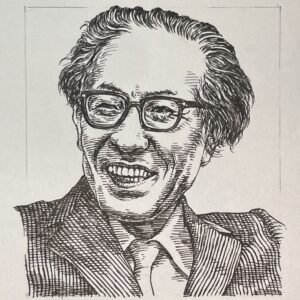



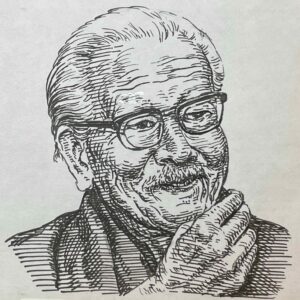


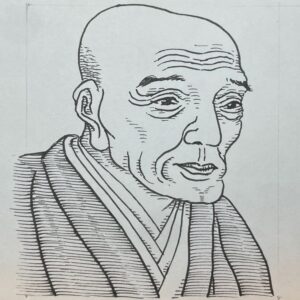




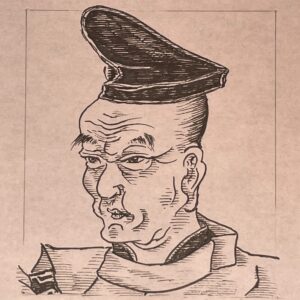

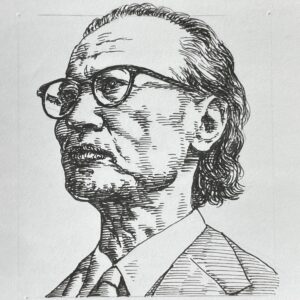

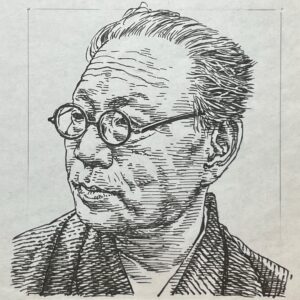







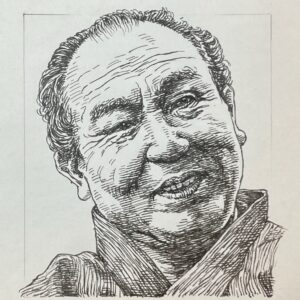
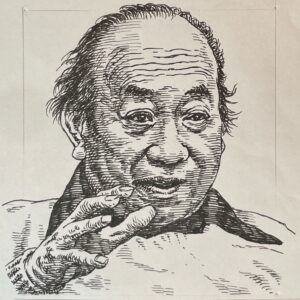
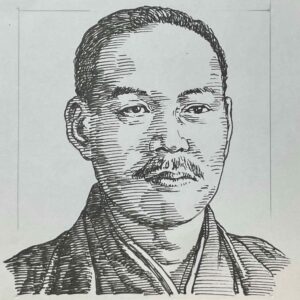
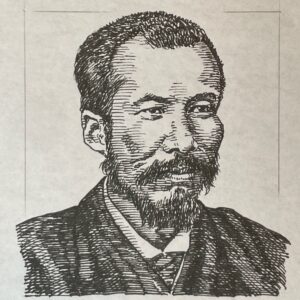
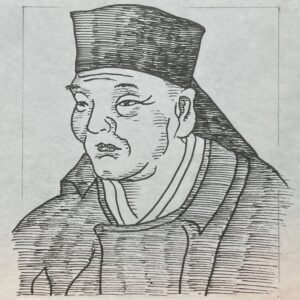
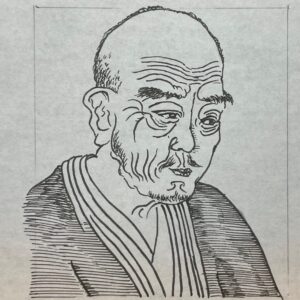
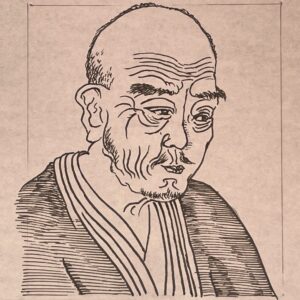
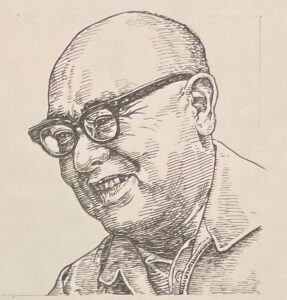
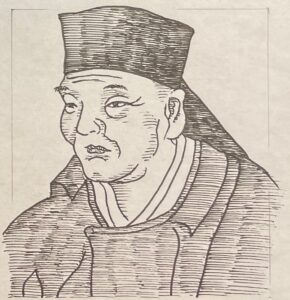

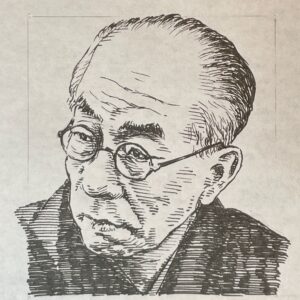
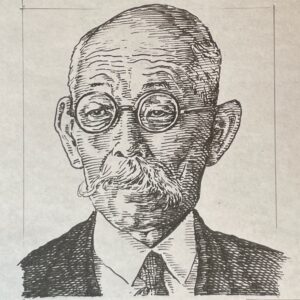
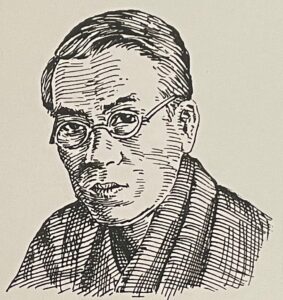
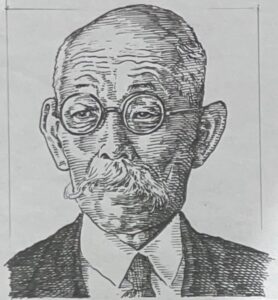
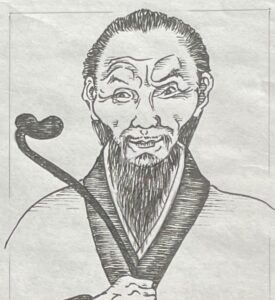

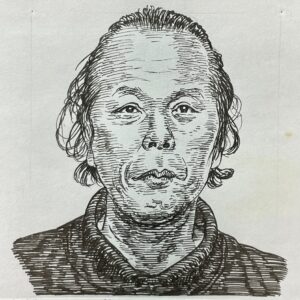


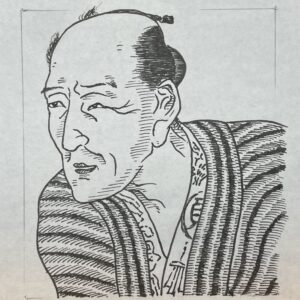
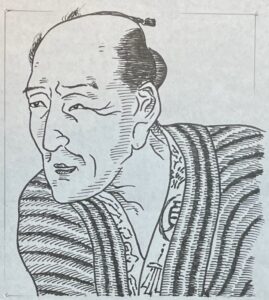


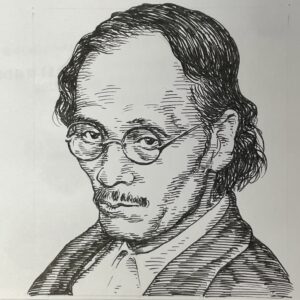
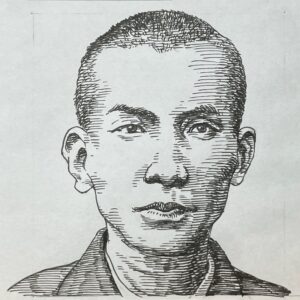


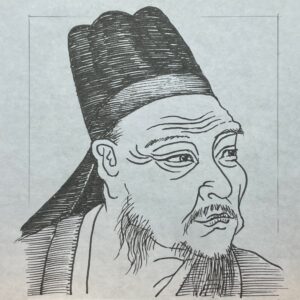
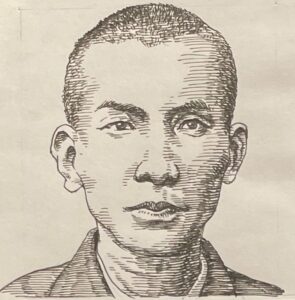
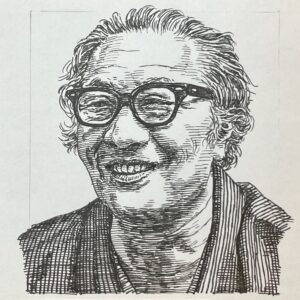

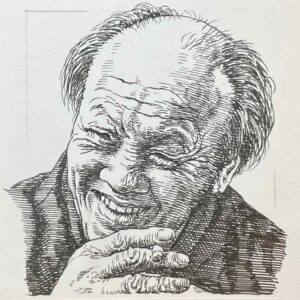
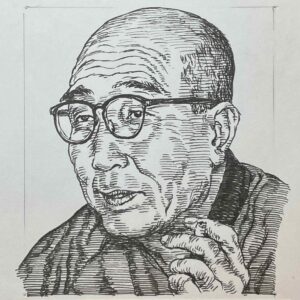


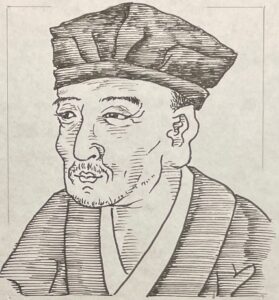
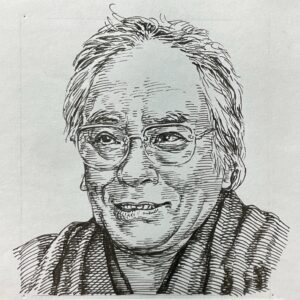

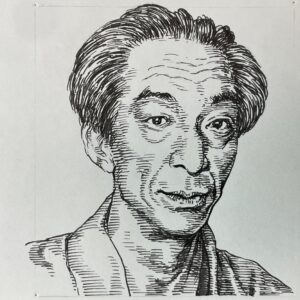
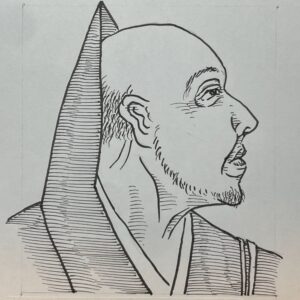
![1920-1992を生きた作詞家であり脚本家。中学卒業後、京都でアニメ映画製作など、職を転々とし、1941(昭和16)年召集され従軍。戦後、東宝の脚本家として「暗黒街の対決(1960)」や特撮映画「モスラ(1961)」などを手がけ、ゴジラシリーズにも名を残した。作詞家としては1958(昭和33)年、日本コロムビアと契約し、歌・小林旭「ダイナマイトが百五十屯(1958)」で鮮烈なデビューをはたす。以後、歌・舟木一夫「学園広場(1963)] 、「銭形平次(1966)」、歌・美空ひばり「柔(1964)」、など、映画やテレビの物語性と共鳴するヒット曲を連発。詞にドラマ性を宿した作風で、昭和歌謡の一翼を彩った。](https://illuststation196.com/wp-content/uploads/2026/01/Shinichi-Sekizawa-300x300.jpeg)