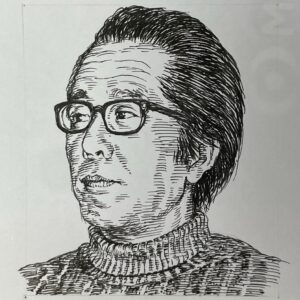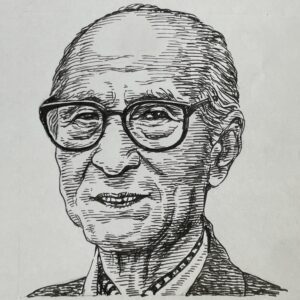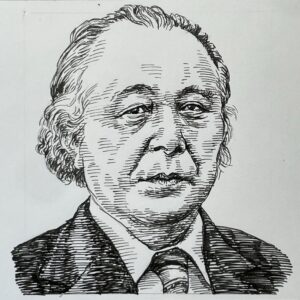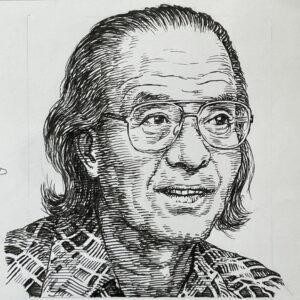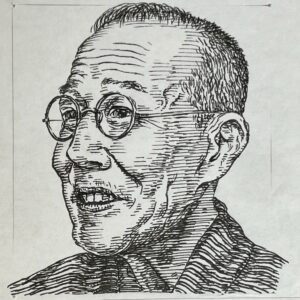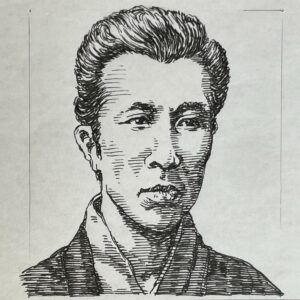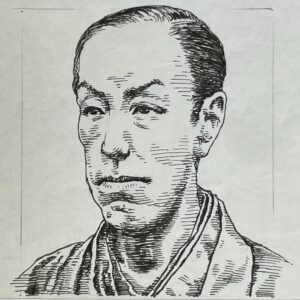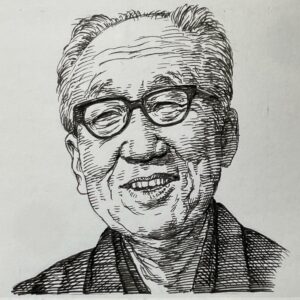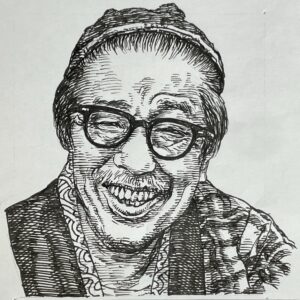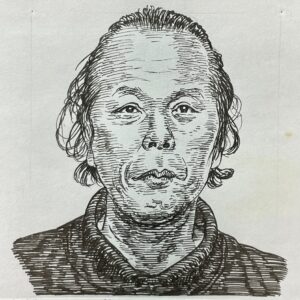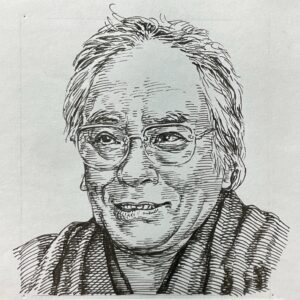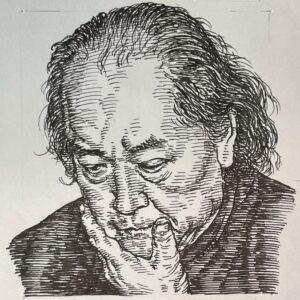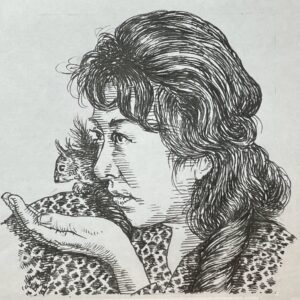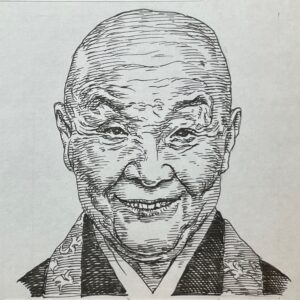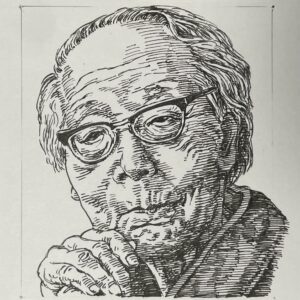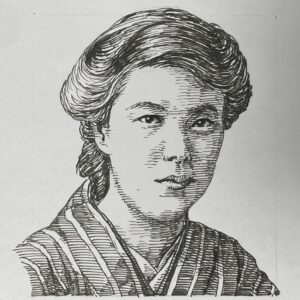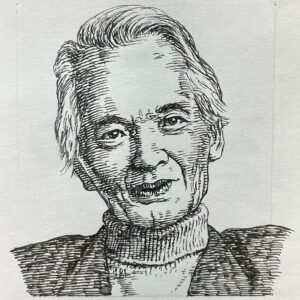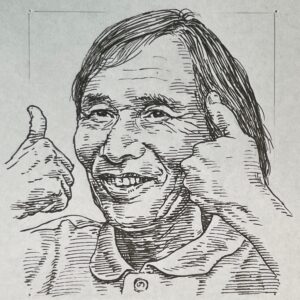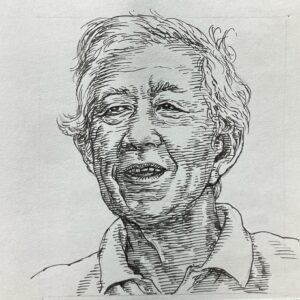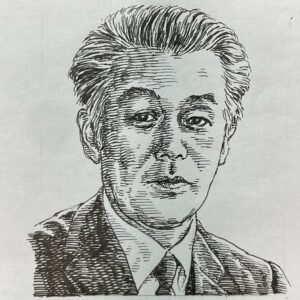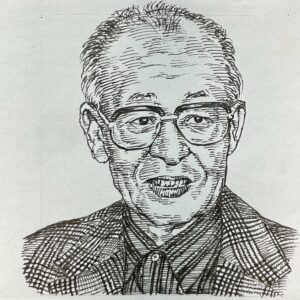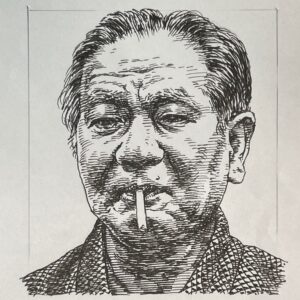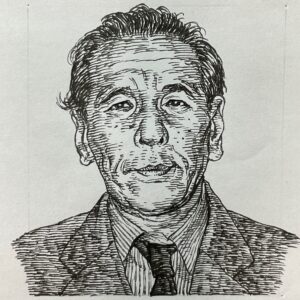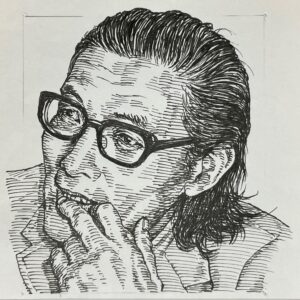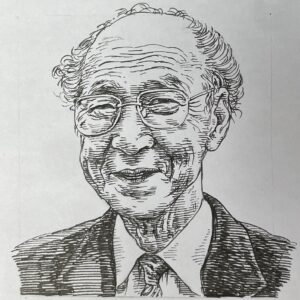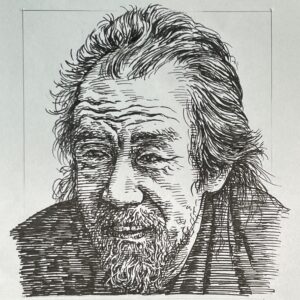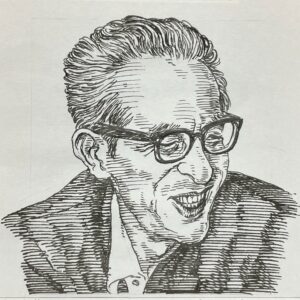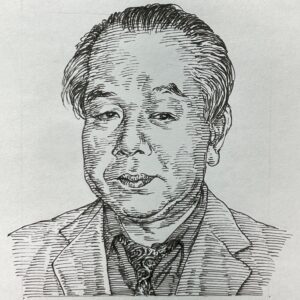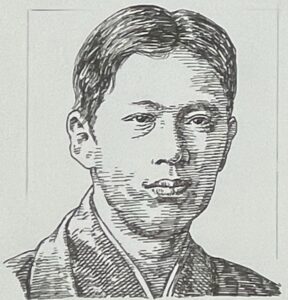松本清張記念館で令和4年度中・高校生対象読書感想文コンクール開催中です
締め切られました2022年9月30日(金)当日の消印有効「砂の器」「顔」「西郷札」どれも書きごたえたっぷりです。
松本清張 Seicyo Matsumoto
ようこそ!フリーイラストポートレートと
歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ
こちらのページでは【文壇発見】
「松本清張」没後30年もドラマの定番 文学の部屋をお楽しみください
松本清張イラストポートレート(Syusuke Galleryより)
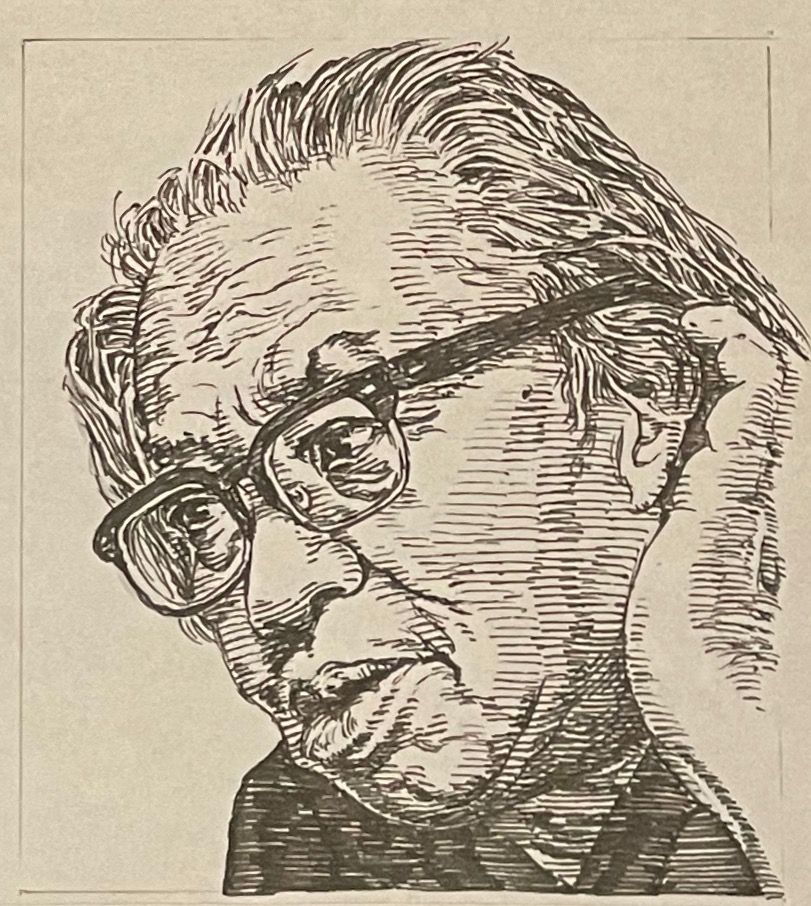
その戦前の半生、目の前にある「生きる」実体験が戦後の万年筆に乗り移り、数々の名作、そして社会を動かしていた清張
※今回いらすとすてーしょんでは広島県を出身地とさせていただきました
行こう松本清張記念館

松本清張記念館
福岡県北九州市小倉北区城内2番3号
TEL:093-582-2761
開館時間:午前9:30~午後6:00(入館は午後5:30まで)
休館日:毎週月曜日(休日の場合は翌日)・年末年始 (12月29日~1月3日)・館内整理日
フィクション、ノンフィクション、評伝、古代史、現代史へと創作の領域を拡大し、驚異的な努力で独自の世界を構築した松本清張(松本清張記念館HPより)
お亡くなりになられてから早30年
いまを生きておられたら「主題」は何を選択されるのか?
想いを駆け巡らせます
文学家・新着偉人(It's New)はこちらから
【文学の部屋|小田 実】昭和時代編.203New!!
【文学の部屋|都筑道夫】昭和時代編.202New!!
【文学の部屋|吉行淳之介】昭和時代編.201New!!
【文学の部屋|川内康範】昭和時代編.200New!!
【文学の部屋|小島直記】昭和時代編.199New!!
【文学の部屋|三木トリロー(鶏郎)】昭和時代編.198New!!
【文学の部屋|扇谷正造】昭和時代編.197New!!
【文学の部屋|花森安治】昭和時代編.196
【文学の部屋|平山蘆江】昭和時代編.195
【文学の部屋|橘 樸】昭和時代編.194
【文学の部屋|桐生悠々】大正時代編.57
【文学の部屋|志賀重昂】明治時代編.47
【文学の部屋|半井桃水】明治時代編.46
【文学の部屋|成島柳北】明治時代編.45
【文学の部屋|加藤楸邨】昭和時代編.193
【文学の部屋|サトウハチロー】昭和時代編.192
【文学の部屋|蔵原惟人】昭和時代編.191
【文学の部屋|山口青邨】大正時代編.56
【文学の部屋|長田幹彦】大正時代編.55
【文学の部屋|つかこうへい】昭和時代編.190
【文学の部屋|寺山修司】昭和時代編.189
【文学の部屋|灰谷健次郎】昭和時代編.188
【文学の部屋|長部日出雄】昭和時代編.187
【文学の部屋|石原慎太郎】昭和時代編.186
【文学の部屋|江藤 淳】昭和時代編.185
【文学の部屋|大岡 信】昭和時代編.184
【文学の部屋|瀬木慎一】昭和時代編.183
【文学の部屋|団 鬼六】昭和時代編.182
【文学の部屋|高橋和巳】昭和時代編.182
【文学の部屋|開高 健】昭和時代編.181
【文学の部屋|野坂昭如】昭和時代編.180
【文学の部屋|権藤芳一】昭和時代編.179
【文学の部屋|なだ いなだ】昭和時代編.178
【文学の部屋|色川武大】昭和時代編.177
【文学の部屋|吉原幸子】昭和時代編.176
【文学の部屋|稲畑汀子】昭和時代編.175
【文学の部屋|有吉佐和子】昭和時代編.174
【文学の部屋|澤地久枝】昭和時代編.173
【文学の部屋|大庭みな子】昭和時代編.172
【文学の部屋|向田邦子】昭和時代編.171
【文学の部屋|岸田衿子】昭和時代編.170
【文学の部屋|瀬戸内寂聴】昭和時代編.169
【文学の部屋|岩谷時子】昭和時代編.168
【文学の部屋|高田敏子】昭和時代編.167
【文学の部屋|白洲正子】昭和時代編.166
【文学の部屋|斎藤 史】昭和時代編.165
【文学の部屋|田中澄江】昭和時代編.164
【文学の部屋|石井桃子】昭和時代編.163
【文学の部屋|矢田津世子】昭和時代編.162
【文学の部屋|円地文子】昭和時代編.161
【文学の部屋|平林たい子】昭和時代編.160
【文学の部屋|佐多稲子】昭和時代編.159
【文学の部屋|大田洋子】昭和時代編.158
【文学の部屋|村山籌子】昭和時代編.157
【文学の部屋|林 芙美子】昭和時代編.156
【文学の部屋|森 茉莉】昭和時代編.155
【文学の部屋|住井すゑ】昭和時代編.154
【文学の部屋|中村汀女】昭和時代編.153
【文学の部屋|壺井 栄】昭和時代編.152
【文学の部屋|宮本百合子】昭和時代編.151
【文学の部屋|宇野千代】昭和時代編.150
【文学の部屋|尾崎 翠】昭和時代編.149
【文学の部屋|吉屋信子】昭和時代編.148
【文学の部屋|森田たま】昭和時代編.147
【文学の部屋|村岡花子】昭和時代編.146
【文学の部屋|野上弥生子】昭和時代編.145
【文学の部屋|バチェラー八重子】昭和時代編.144
【文学の部屋|金子みすゞ】大正時代編.53
【文学の部屋|今井邦子】大正時代編.52
【文学の部屋|柳原白蓮】大正時代編.51
【文学の部屋|田村俊子】大正時代編.51
【文学の部屋|長谷川時雨】明治時代編.44
【文学の部屋|樋口一葉】明治時代編.43
【文学の部屋|中島歌子】明治時代編.42
【文学の部屋|多木浩二】昭和時代編.143
【文学の部屋|城山三郎】昭和時代編.142
【文学の部屋|藤沢周平】昭和時代編.141
【文学の部屋|北 杜夫】昭和時代編.140
【文学の部屋|吉野 弘】昭和時代編.139
【文学の部屋|いいだ もも】昭和時代編.138
【文学の部屋|星 新一】昭和時代編.137
【文学の部屋|山口 瞳】昭和時代編.136
【文学の部屋|三島由紀夫】昭和時代編.135
【文学の部屋|長崎源之助】昭和時代編.134
【文学の部屋|安部公房】昭和時代編.133
【文学の部屋|池波正太郎】昭和時代編.132
【文学の部屋|司馬遼太郎】昭和時代編.131
【文学の部屋|遠藤周作】昭和時代編.130
【文学の部屋|田村隆一】昭和時代編.129
【文学の部屋|中井英夫】昭和時代編.128
【文学の部屋|中川正文】昭和時代編.127
【文学の部屋|五味康祐】昭和時代編.126
【文学の部屋|塚本邦雄】昭和時代編.125
【文学の部屋|安岡章太郎】昭和時代編.124
【文学の部屋|有馬頼義】昭和時代編.123
【文学の部屋|福永武彦】昭和時代編.122
【文学の部屋|土屋隆夫】昭和時代編.121
【文学の部屋|斎藤隆介】昭和時代編.120
【文学の部屋|梅崎春生】昭和時代編.119
2022年放送 松本清張スペシャル
【作品概要】禎子と結婚したばかりの憲一が、社の仕事の引継ぎのため前任地の金沢へ行ったまま帰ってこない。禎子は金沢へ行き、夫の同僚・本多と調べる。憲一の兄・宗太郎も東京から加わるが、金沢郊外で何者かに毒殺される。禎子の母が「憲一さんは昔、立川で巡査をしていたよ」と禎子に電話してきた。売春婦を取り締まっていたらしい。金沢時代、憲一は室田煉瓦の室田室長を親しくしていたと聞き、禎子が室田を訪ねる。受付の久子が売春婦の使う特殊な英語で外人客に対応している。
【出演者】禎子…真野あずさ、憲一…並木史朗、宗太郎…岸部一徳、北村警部補…林隆三、ほか
【スタッフ】原作…松本清張、監督…鷹森立一、ほか
【初回放送】日本テレビ1991年7月9日
BS日テレ松本清張スペシャル公式HPより抜粋

放送終了しました
○放送終了NHK BSプレミアム 7月23・24日二夜連続
そして待望の「混声の森」現代にアレンジしてドラマ化決定。
https://www.nhk.or.jp/dramatopics-blog/8000/460324.html
広告コーナー
いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により
運営させていただいております
皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます
いらすとすてーしょん検索コーナー
いらすとすてーしょん検索コーナー
いらすとすてーしょん検索コーナー
新着偉人(It's New)
新たに公開のイラストポートレートをご覧ください
【文学の部屋|小田 実】昭和時代編.203New!!
【文学の部屋|都筑道夫】昭和時代編.202
1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓
2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です
2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします