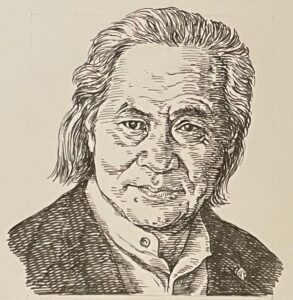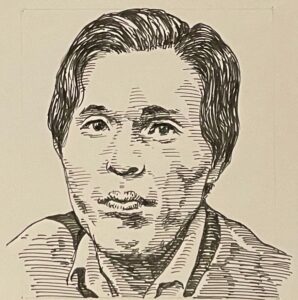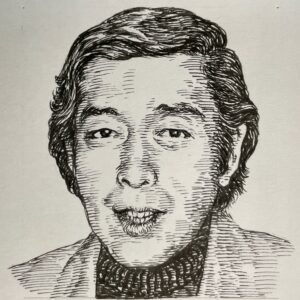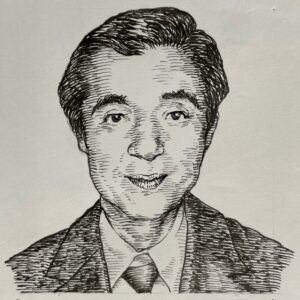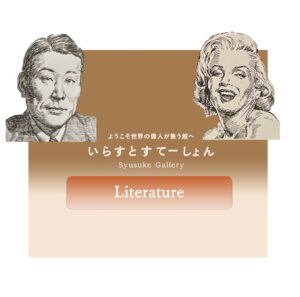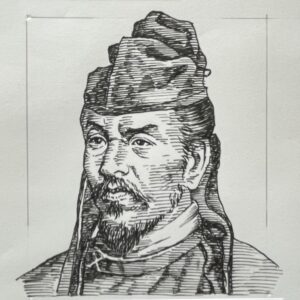井原西鶴
Saikaku Ihara(1642-1693)
ようこそ!フリーイラストポートレートと
歴史の停車場いらすとすてーしょんへ
こちらのページでは【文学の部屋|井原西鶴】
好きやねん大阪文学の祖 をお楽しみください
井原西鶴イラストポートレート
イラストポートレート Syusuke Galleryより
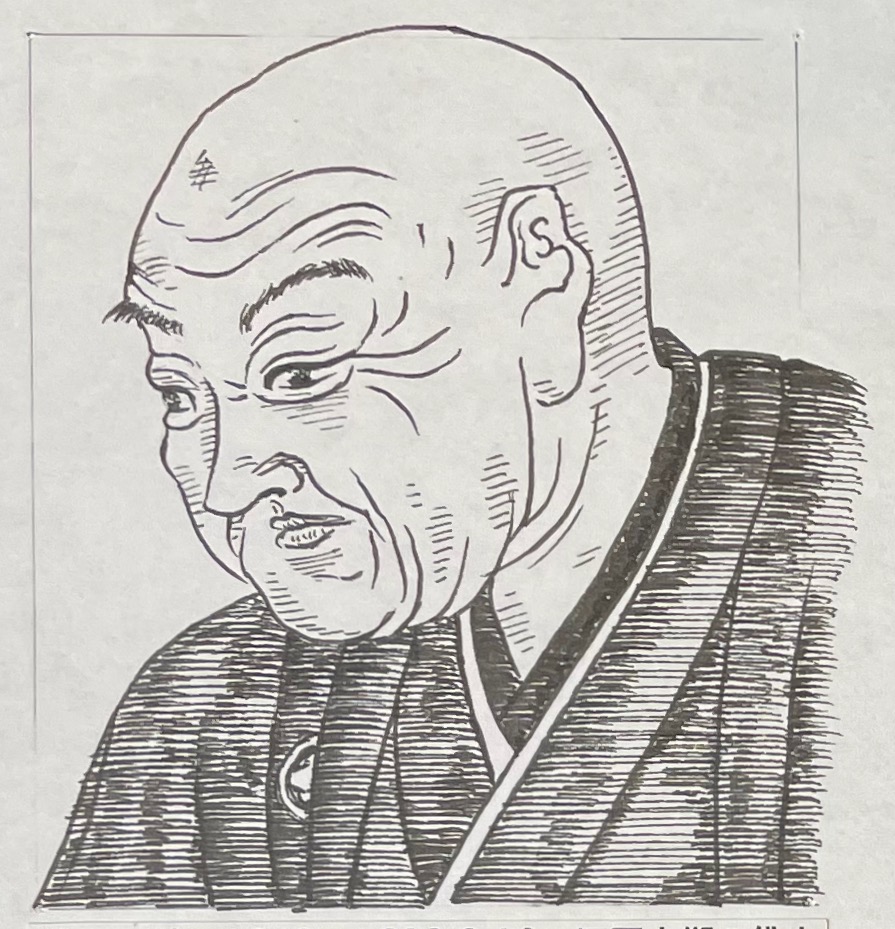
※出生地は大阪府の説もあります
そして小説というジャンルもない江戸時代に
日本で初めてベストセラー小説を生み出した
浮世草子「好色一代男」の作者
わたし、織田作之助がめっちゃ影響を受けました
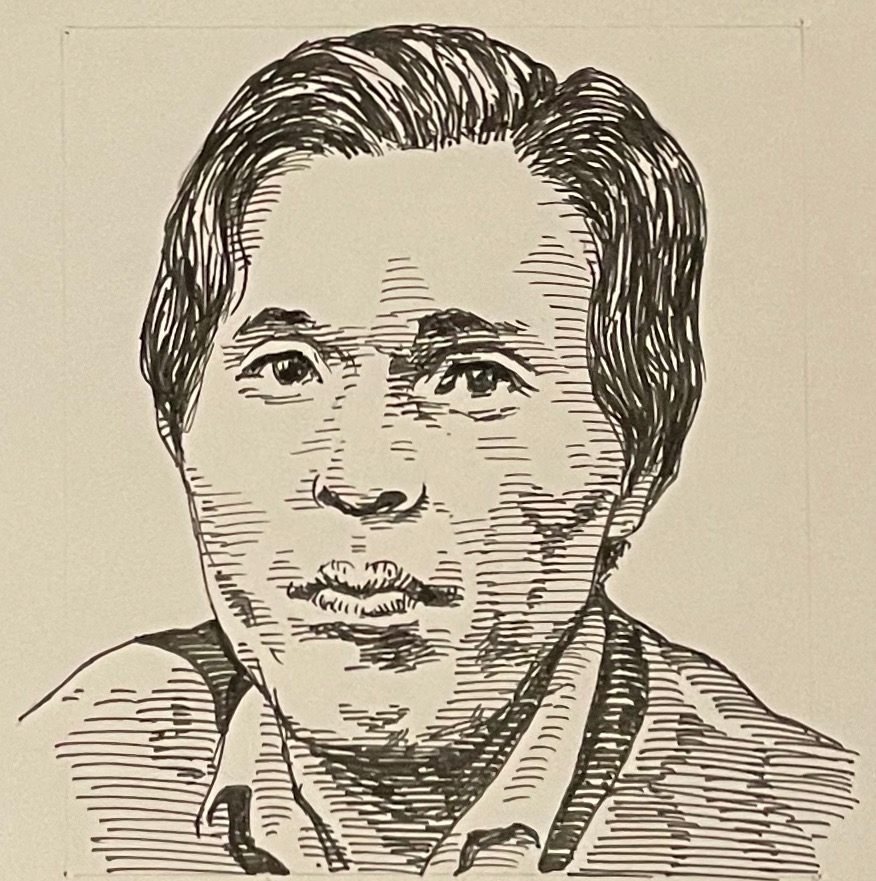
どない?
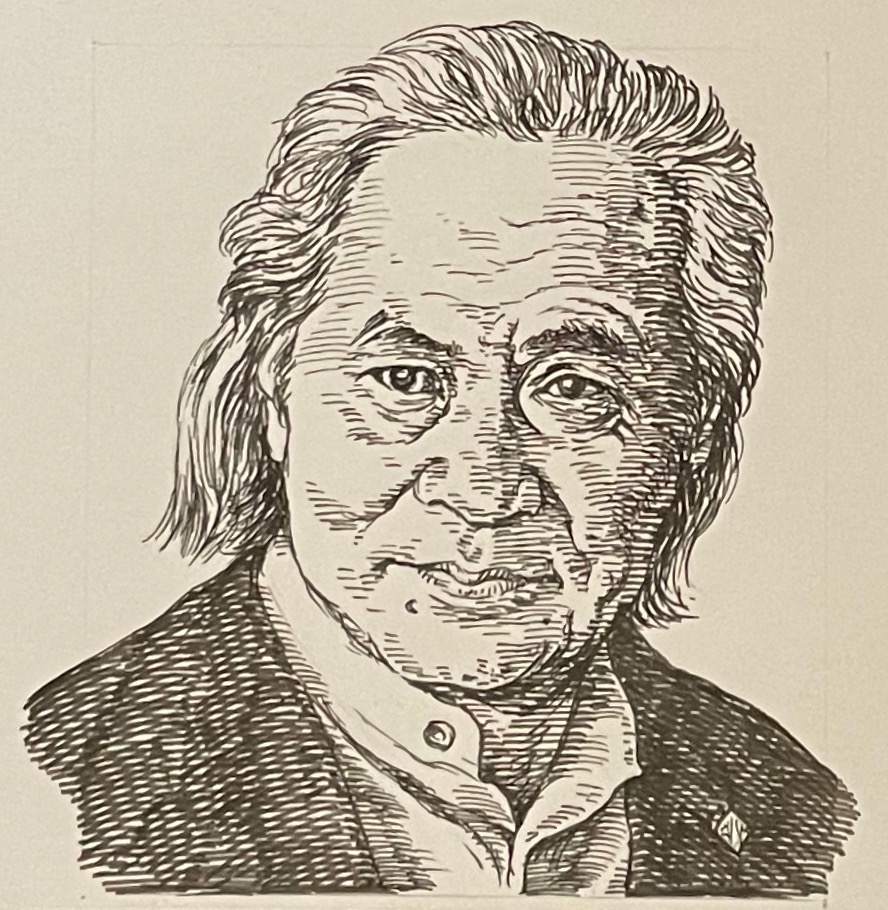
織田作之助さん、おいでませ!
【ファインダーの巨匠|林 忠彦】文壇を輝かせた男 写真家の部屋
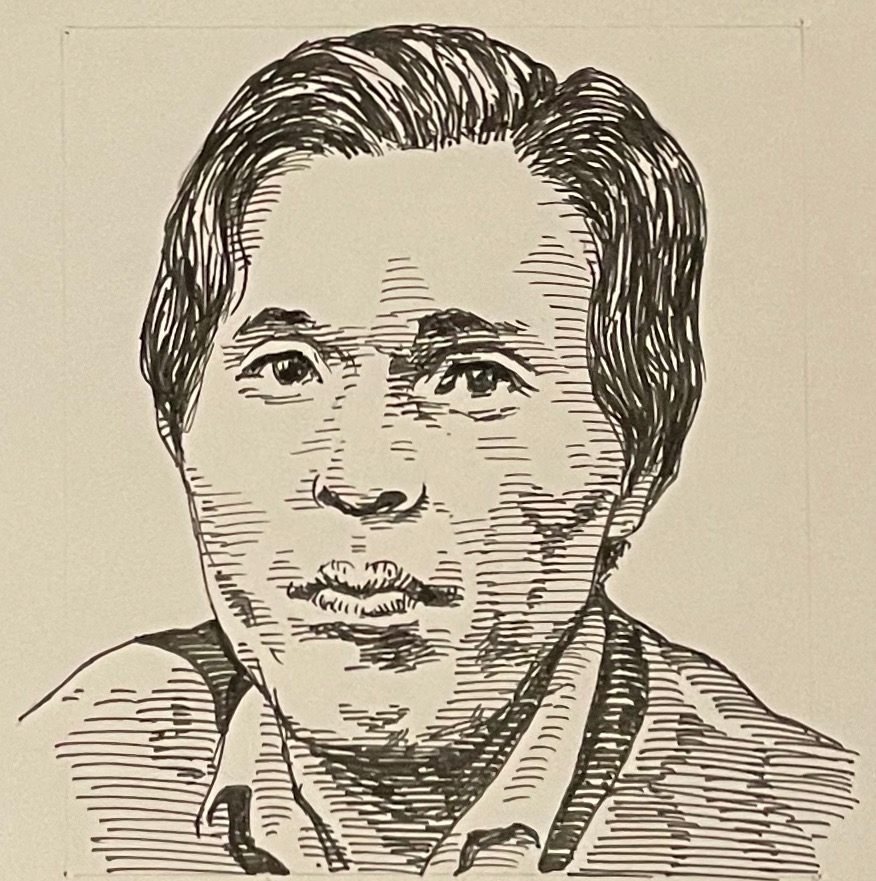
ぼちぼちでんかぁ
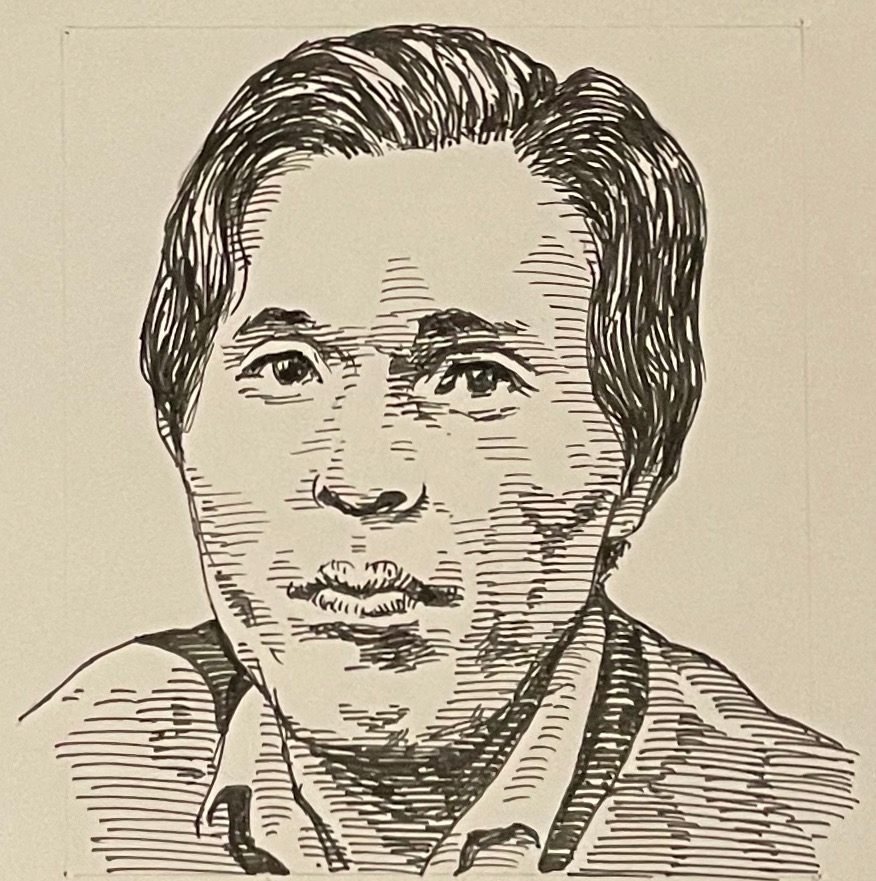
今日はわたしの師匠みたいなもん
井原西鶴せんせやぁ
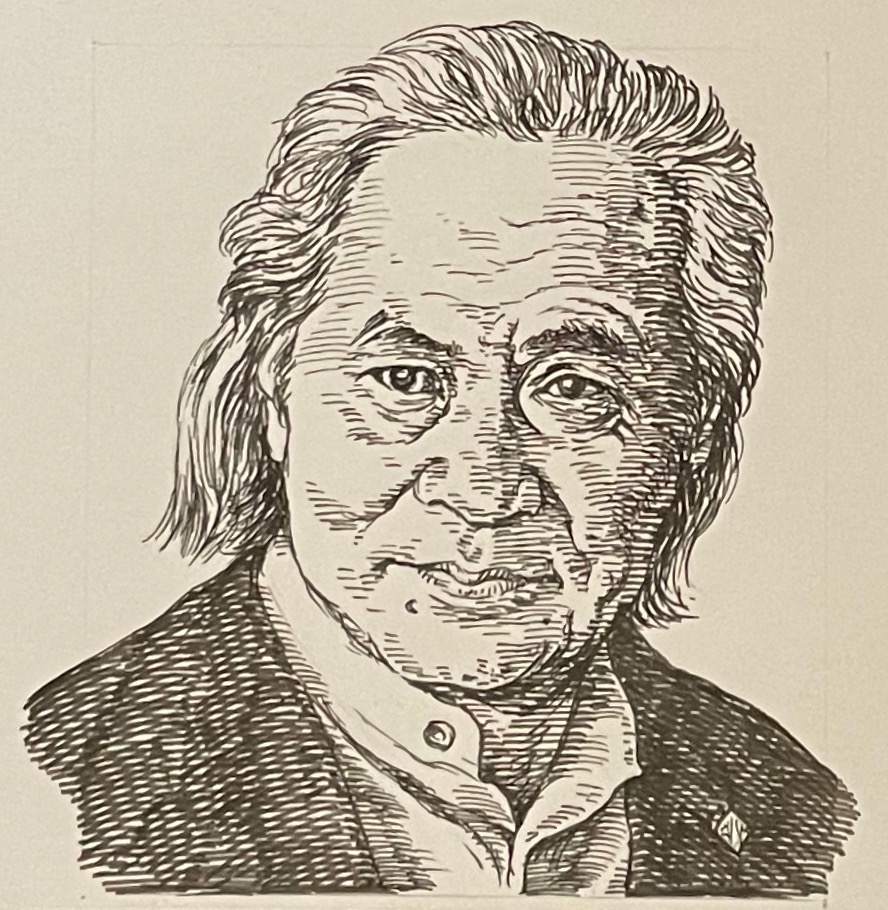
オダサクさん、井原西鶴文学にハマってましたもんな
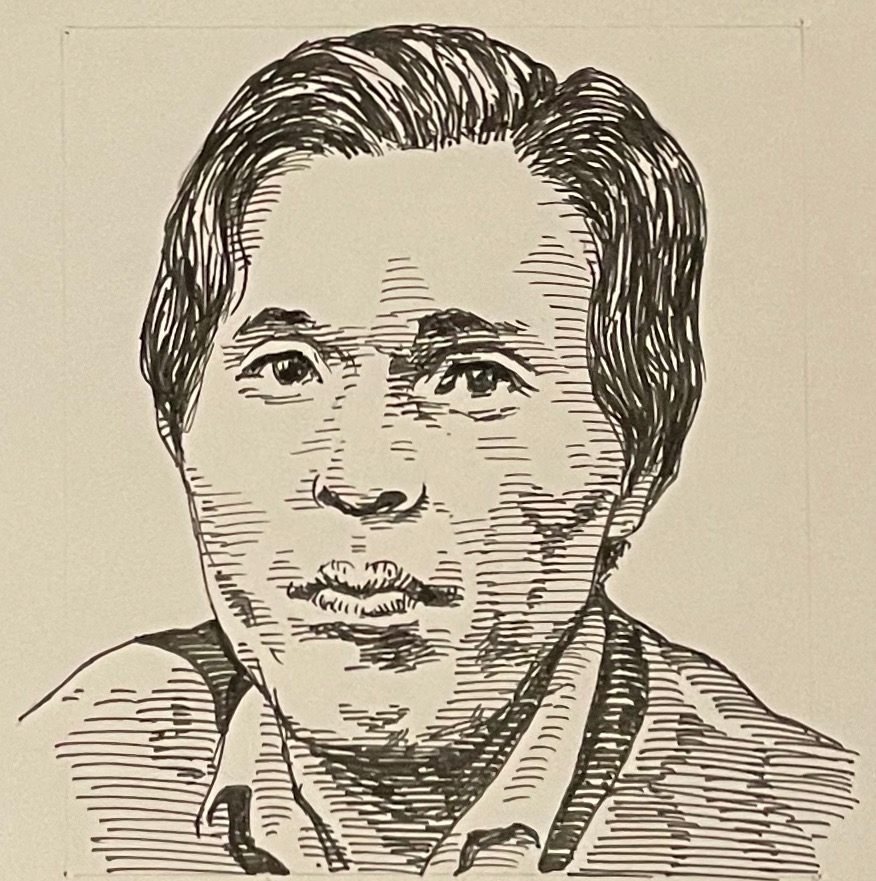
なんちゅうかぁ
生き方っていうか、他人とは思えなくてなぁ
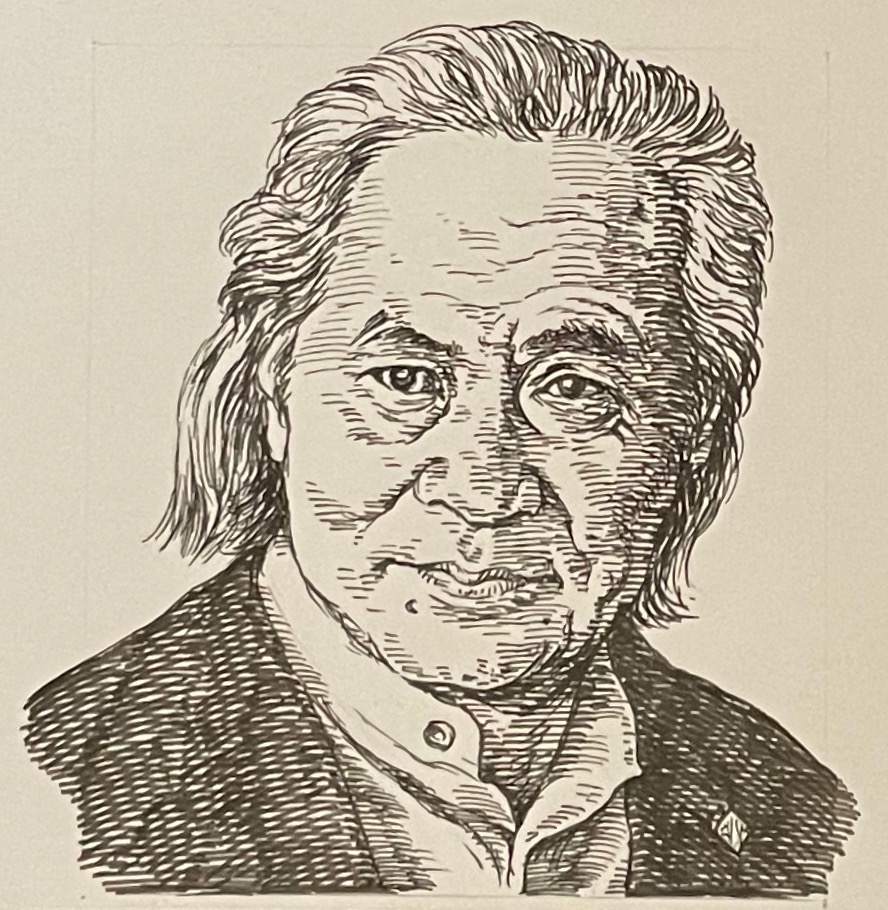
それで「夫婦善哉」をお書きになった
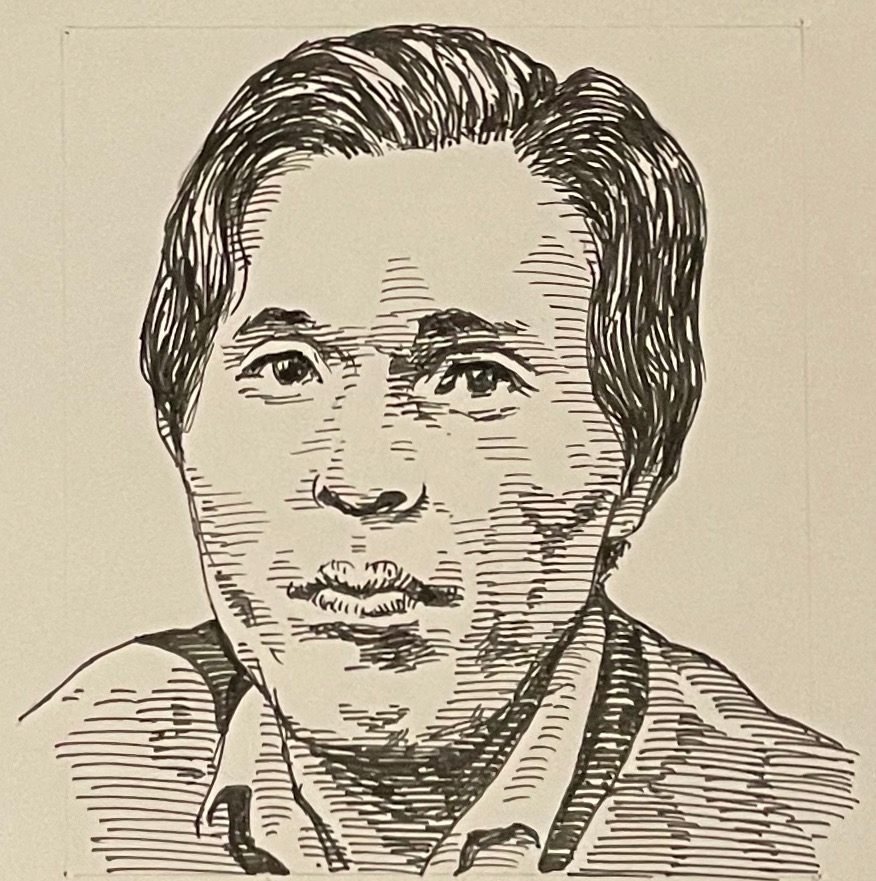
まっ、パクった訳ではないでぇ
井原西鶴せんせの「世間胸算用」をしっかり世襲したんや
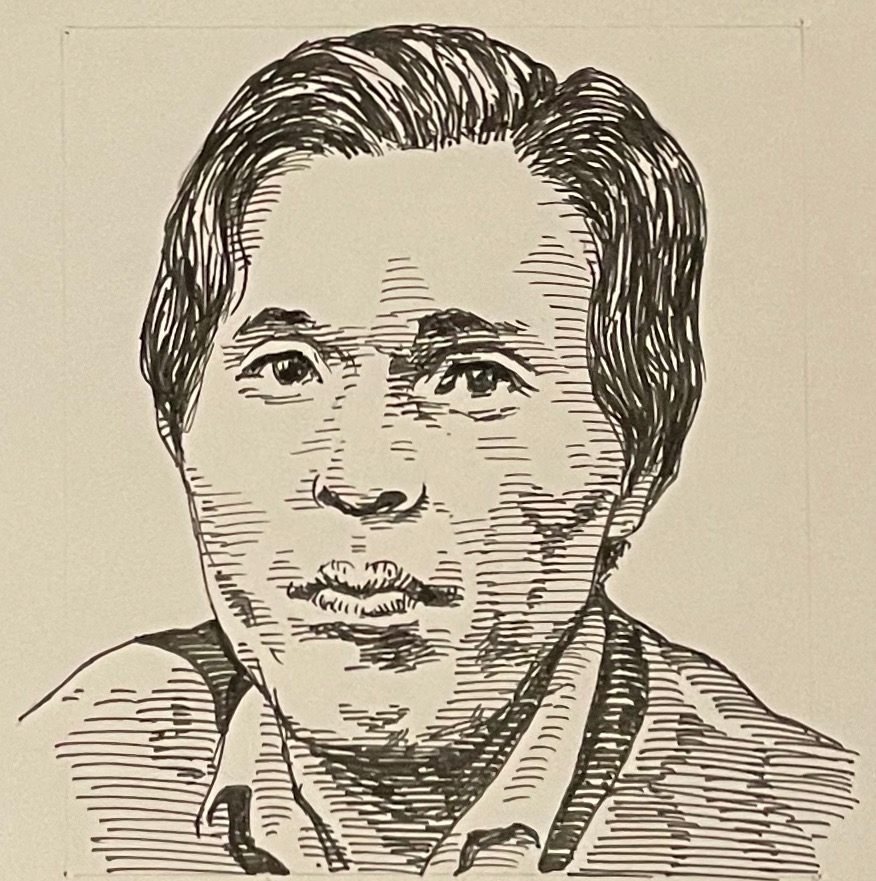
詳しくはこちらをみてな
【文壇発見|織田作之助】好きやねん大阪文学
代表作はなんといっても
好色一代男
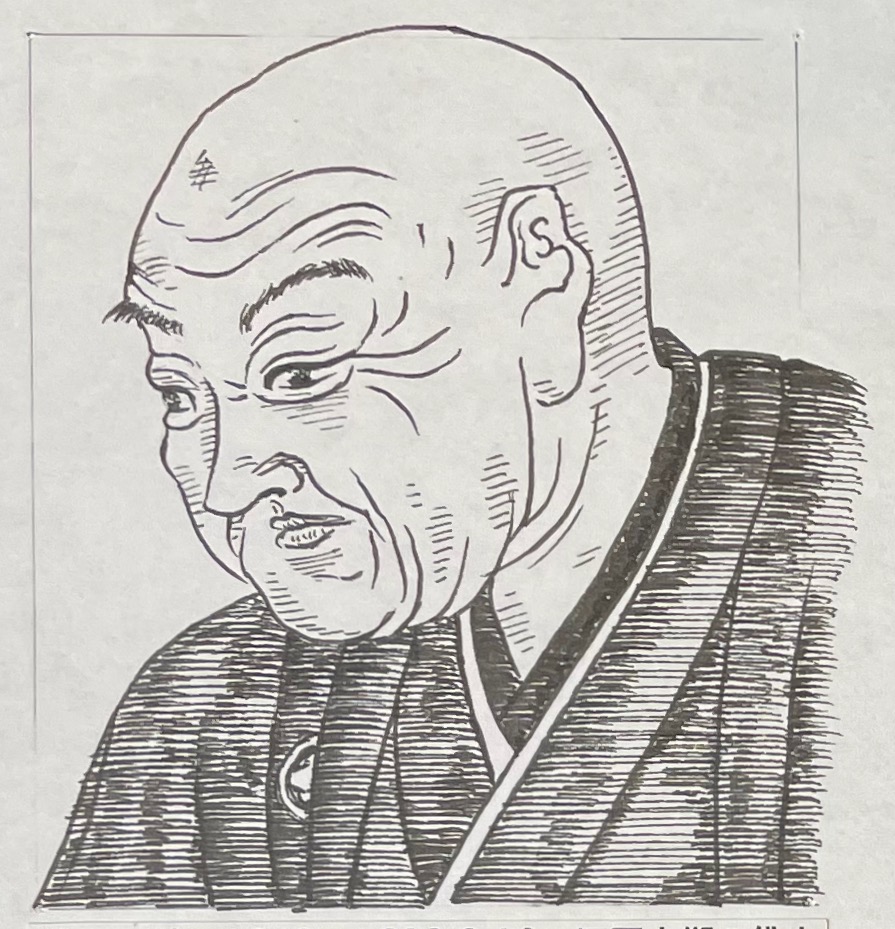
今日は私に会いに来てくれてありがとさん
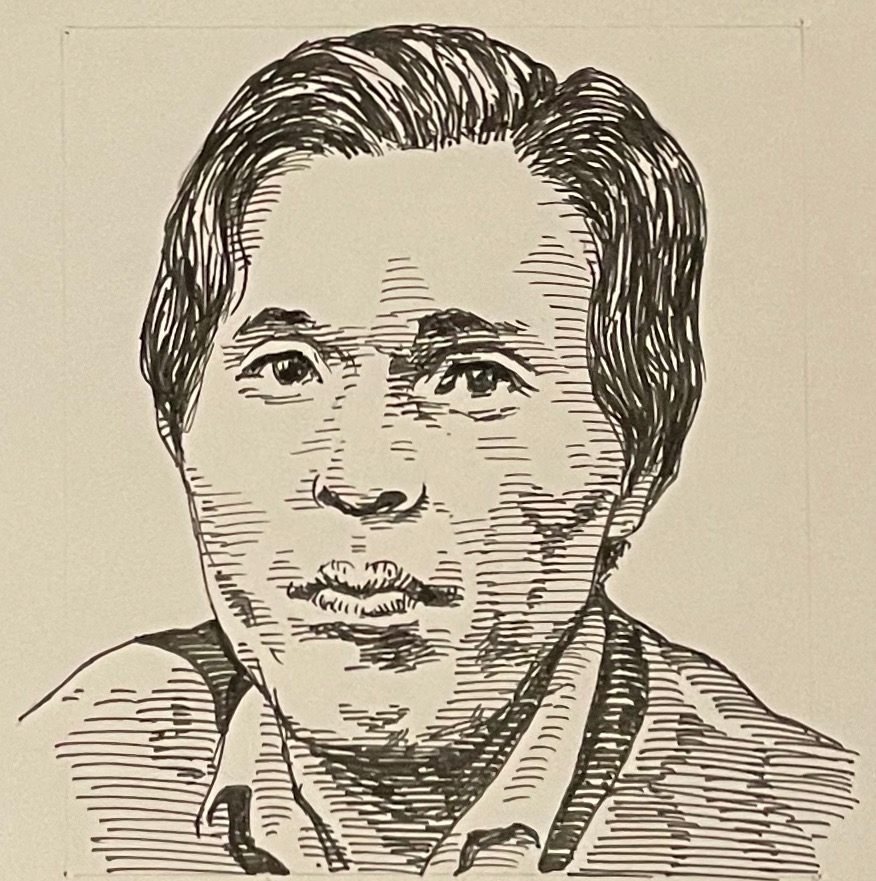
こちらこそ!師匠!
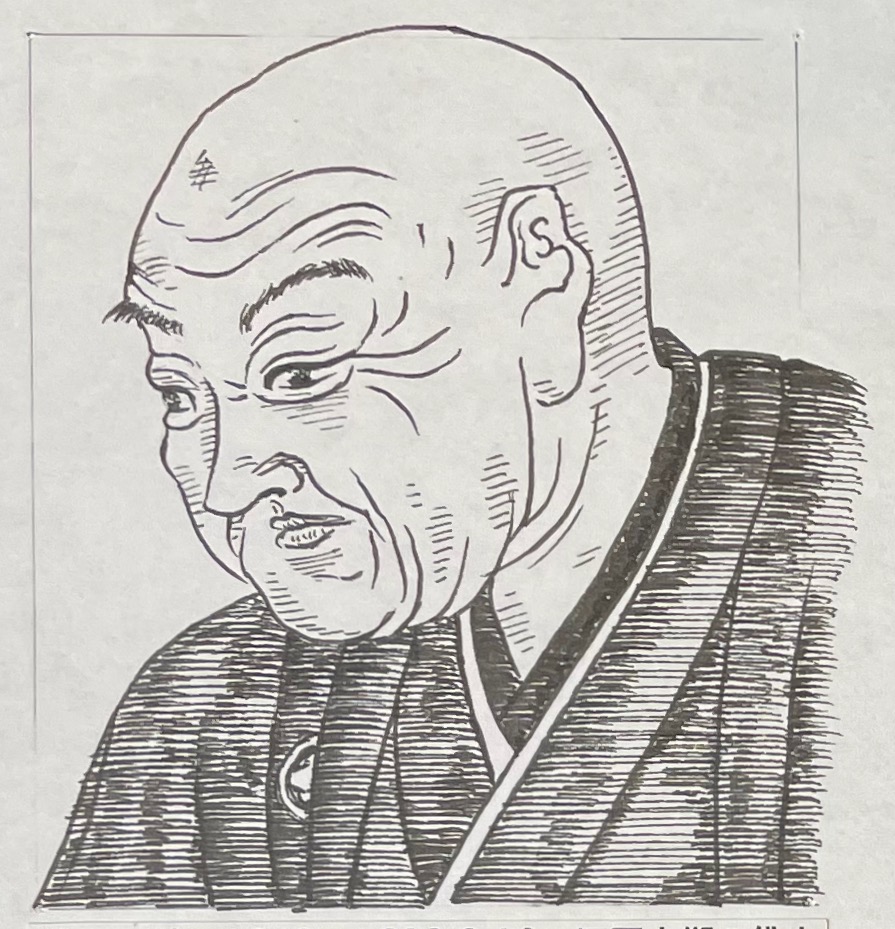
41歳で発表した第一作目の浮世草子「好色一代男」
あんなに当たるとは思っておらんかった
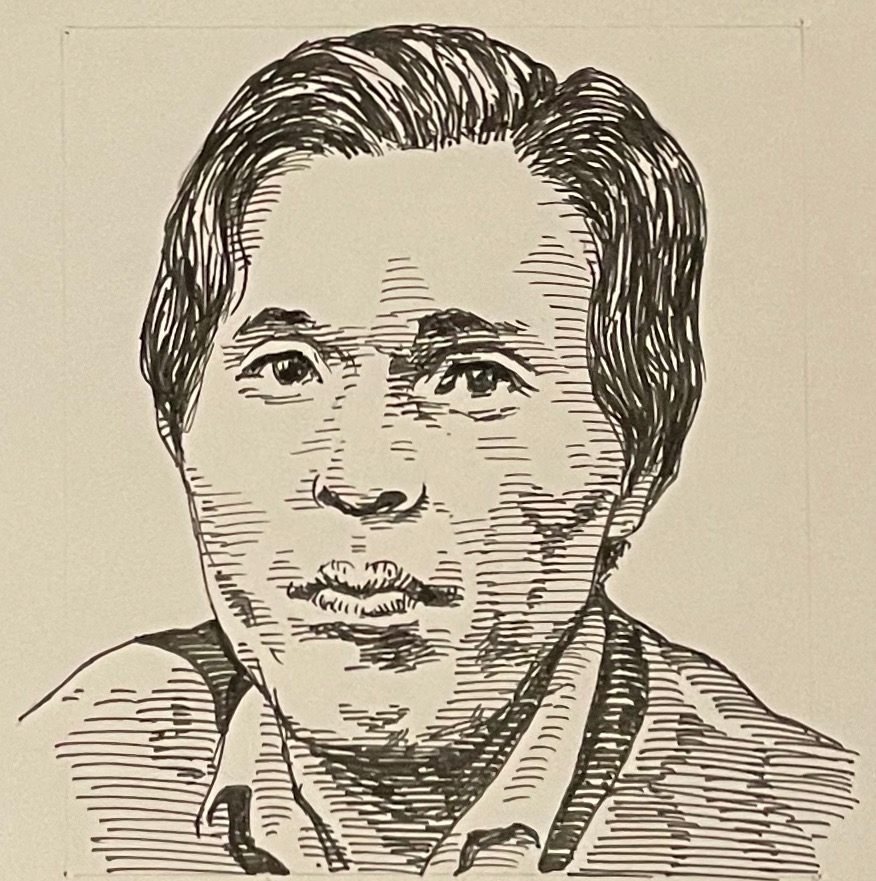
あの時代の上方はまさにバブル絶頂期でしたもんね
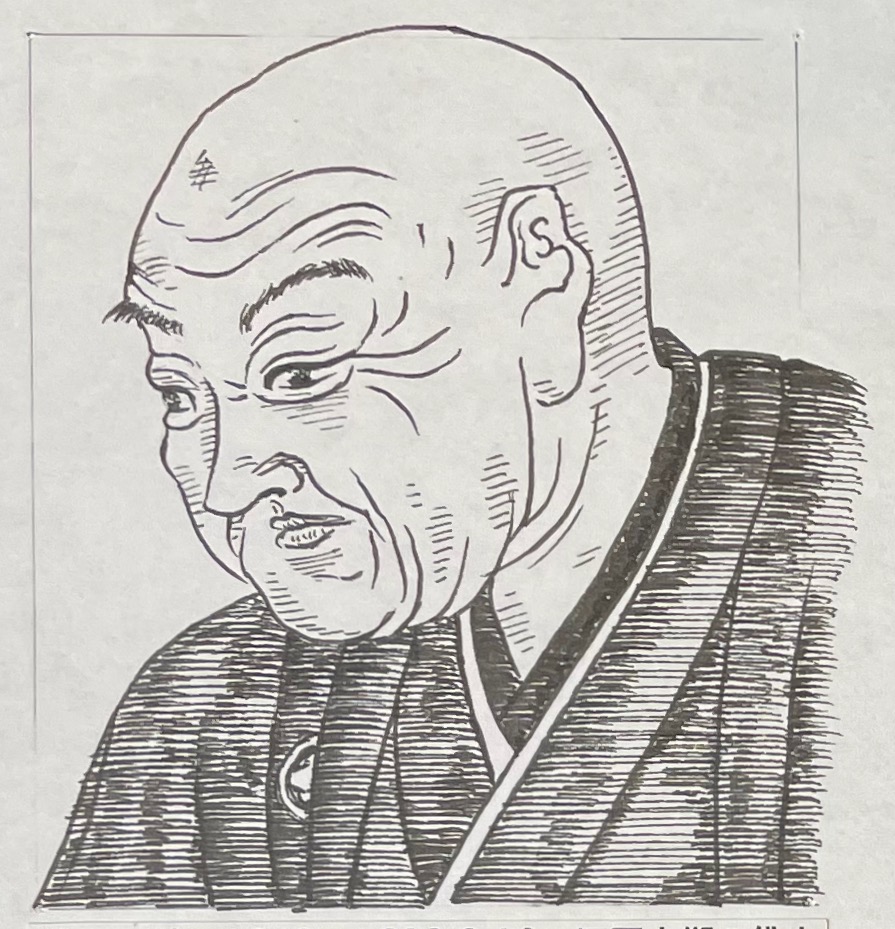
俳諧で培ったスキルを存分に活かせたのも大きかったな
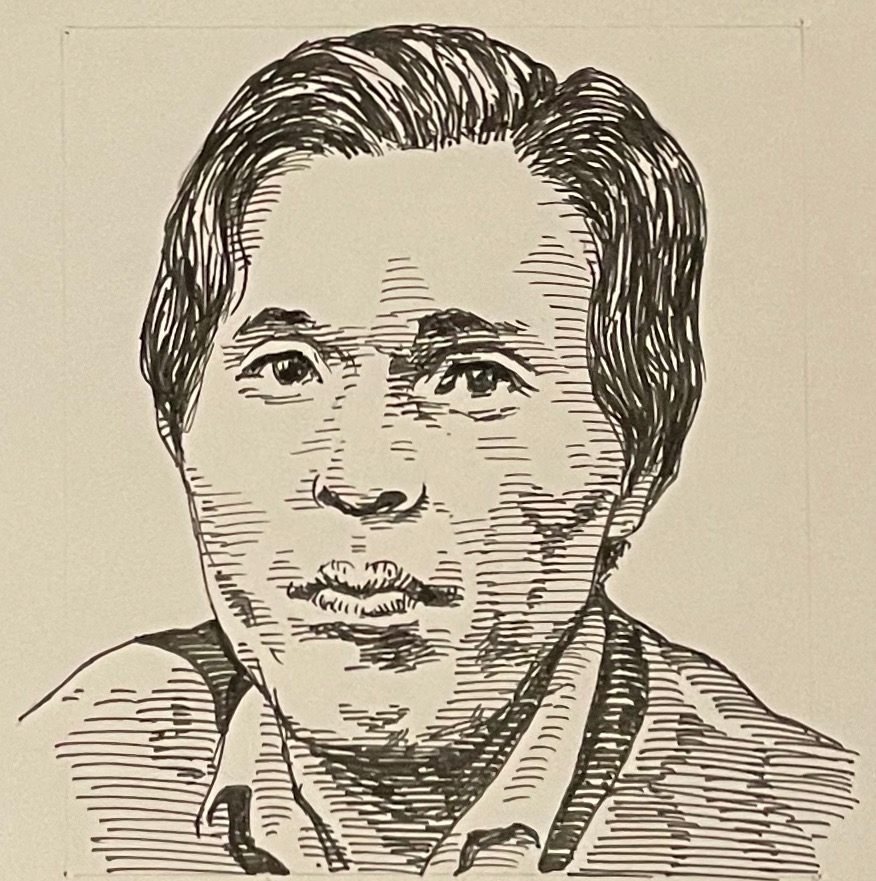
なんと言っても主人公の「世之介」ここでは書けないくらいの男で…
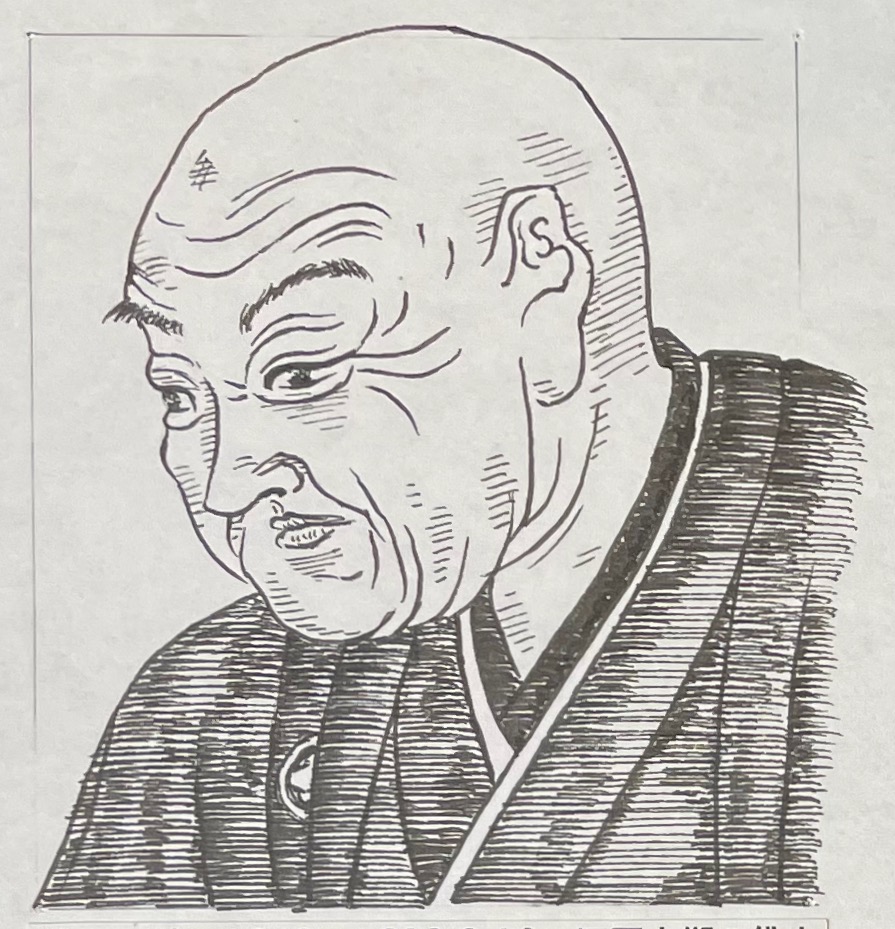
世之介が7歳からスタートさせて60歳までの生涯を54章で書き上げたんだ
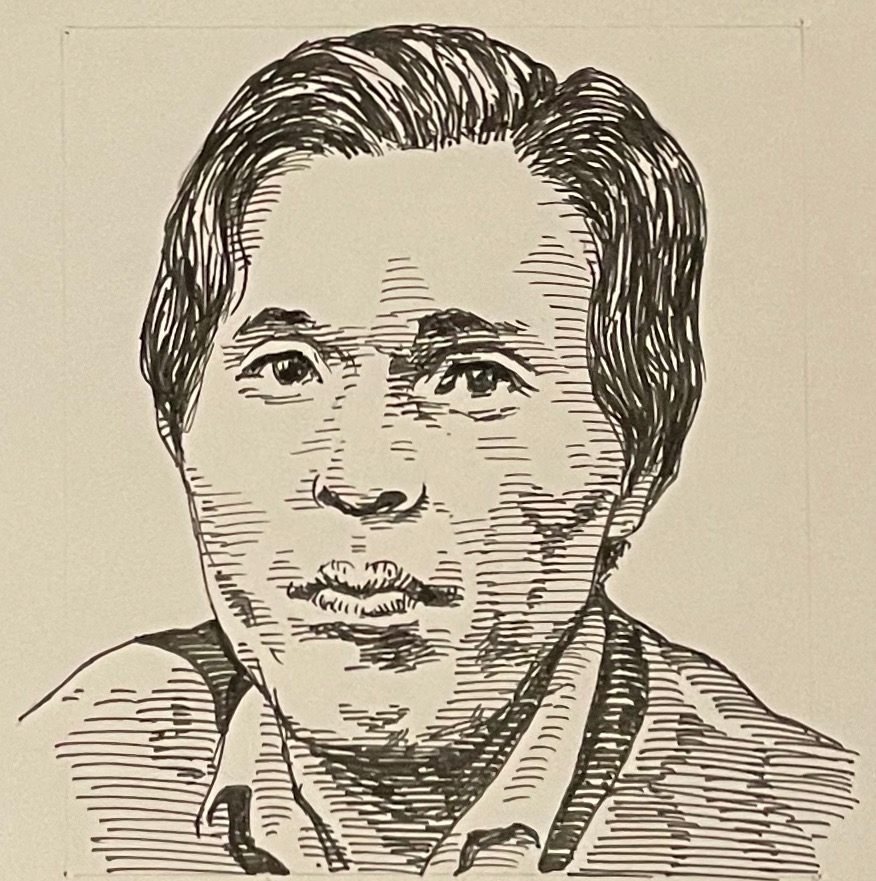
54…それって、まさか源氏物語の54帖に合わせたとかぁ
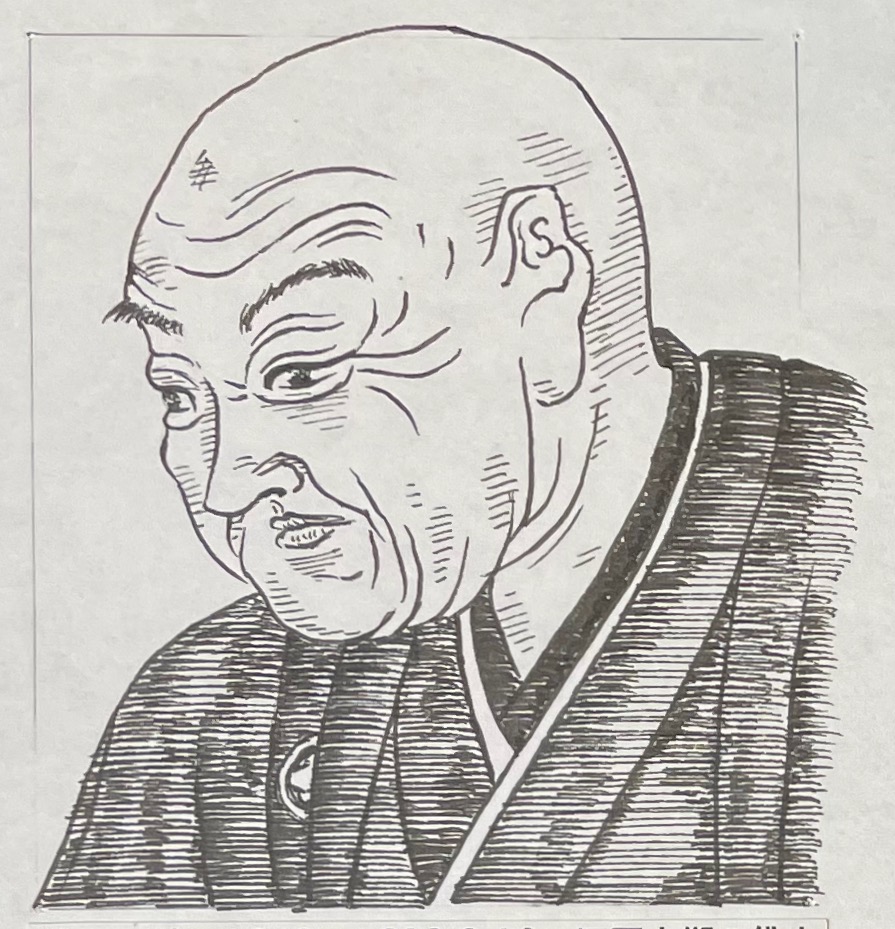
おまえさんの想像に任せるよ
浮世草子は1682年、井原西鶴「好色一代男」刊行から約100年続きます。そして、上方を中心として700あまりの草子(今で言うところの読み物)が刊行されました。
まさに上方文学が大いに栄えたといえます。
広告コーナー
いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により
運営させていただいております
皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます
いらすとすてーしょん検索コーナー
文学者・新着偉人(It's New)はこちらから
【文学の部屋|山上路夫】昭和時代編.232
【文学の部屋|水島 哲】昭和時代編.231
【文学の部屋|横井 弘】昭和時代編.230
【文学の部屋|水木かおる】昭和時代編.229
文学の部屋へようこそ
出身国別、都道府県でお届けしています
文学の部屋 Literature
文学の部屋Literatureへようこそ。SyusukeGalleryよりイラストポートレートをお届けさせていただきます。
いらすとすてーしょん検索コーナー
いらすとすてーしょん検索コーナー
新着偉人(It's New)
新たに公開のイラストポートレートをご覧ください
【政治の部屋|和気清麻呂】奈良時代編.2New!!
【政治の部屋|藤原武智麻呂】奈良時代編.1
2026年2月17日から、政治の部屋より古墳時代からの政治家をお届けしています↓
2026年2月16日まで、文学の部屋より飛鳥~昭和時代に活躍した文学者をお届けしました↓

シュー(Syu)です
2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします