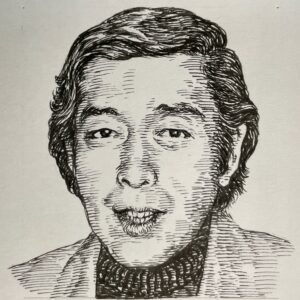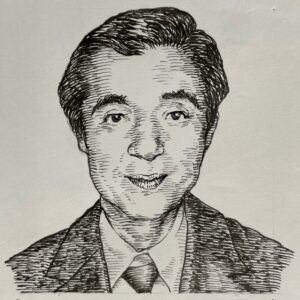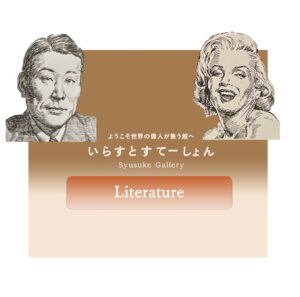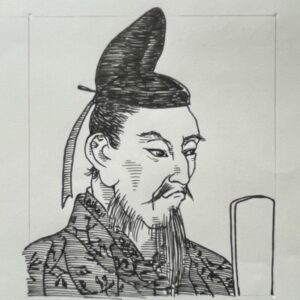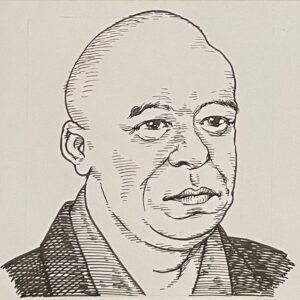太宰 治 Osamu Dazai
ようこそ!フリーイラストポートレートと歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ
こちらのページでは【文壇発見|太宰 治】6月19日生誕日は桜桃忌 をお楽しみください
太宰 治
イラストポートレート Syusuke Galleryより

当時の流行作家として時代の寵児は今なら何を描くのか!?
6月19日生誕日は桜桃忌
太宰 治の肖像画!?
2022年6月に流れたこのニュース
もうご覧になられましたか?
- 初公開
- 昭和の文壇を牽引された編集者の一人「石井 立(Tatsu Ishii)1923-1964」氏は筑摩書房で太宰治の担当であった。
その遺品から太宰が描いた肖像画が三鷹市に寄贈。
2022年6月4日より三鷹市美術ギャラリー 太宰治展示室此の小さな家で初公開。晩年の作品とされていますが、モデルは誰?
そして太宰の忌日桜桃忌6月19日は間も無くやってきます。
※上記内容は2022年6月2日日本経済新聞夕刊改してお届けしました。

三鷹市美術ギャラリー 太宰治展示室此の小さな家
太宰治展示室は「合田佐和子展 帰る途もつもりもない」の開催に伴い、2023年1月17日(火)から4月7日(金)まで休室とのことです
詳しくは公式HPをご参照ください
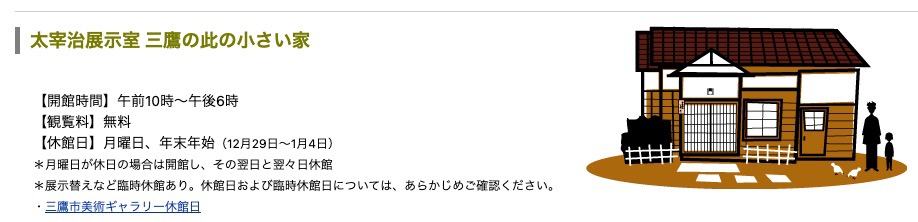
文学家・新着偉人(It's New)はこちらから
【文学の部屋|山上路夫】昭和時代編.232
2026-02-16
【文学の部屋|水島 哲】昭和時代編.231
2026-02-15
【文学の部屋|横井 弘】昭和時代編.230
2026-02-14
【文学の部屋|水木かおる】昭和時代編.229
2026-02-13
文学の部屋へようこそ
出身国別、都道府県でお届けしています
文学の部屋 Literature
文学の部屋Literatureへようこそ。SyusukeGalleryよりイラストポートレートをお届けさせていただきます。
広告コーナー
いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により運営させていただいております
皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます
いらすとすてーしょん検索コーナー
いらすとすてーしょん検索コーナー
新着偉人(It's New)
新たに公開のイラストポートレートをご覧ください
【政治の部屋|菅原道真】平安時代編.3New!!
2026-02-27
【政治の部屋|藤原長良】平安時代編.2
2026-02-26
2026年2月17日から、政治の部屋より古墳時代からの政治家をお届けしています↓
2026年2月16日まで、文学の部屋より飛鳥~昭和時代に活躍した文学者をお届けしました↓

シュー(Syu)です
2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします