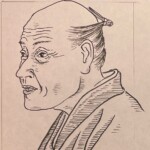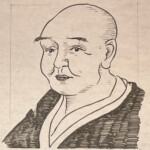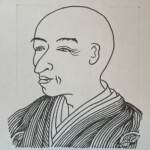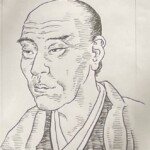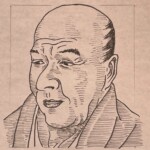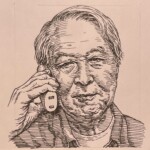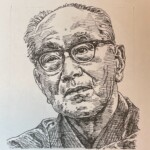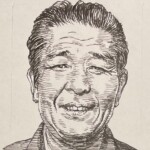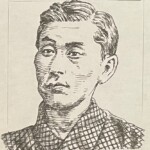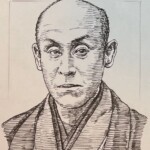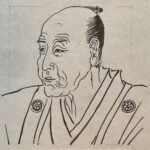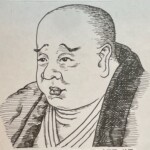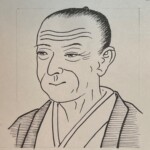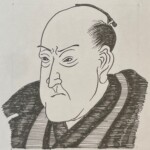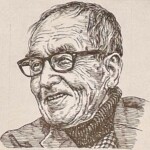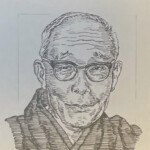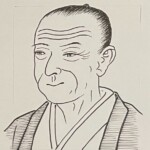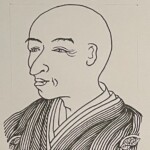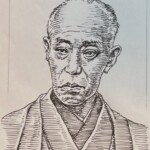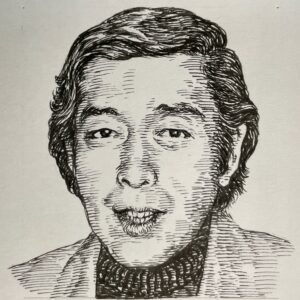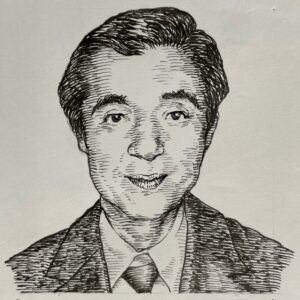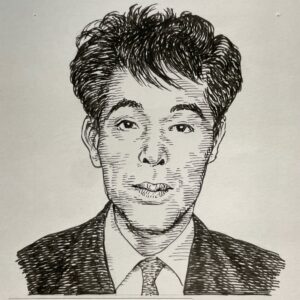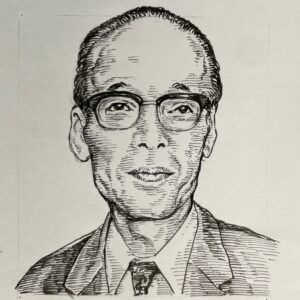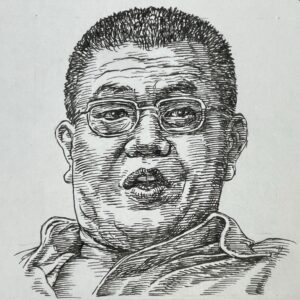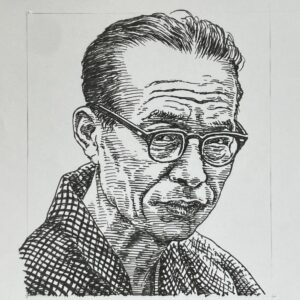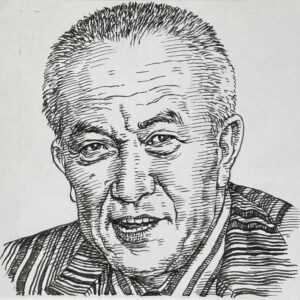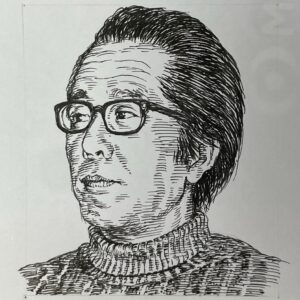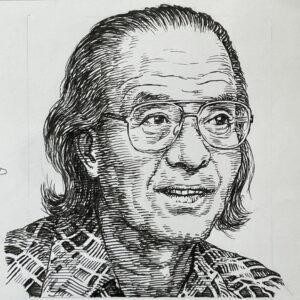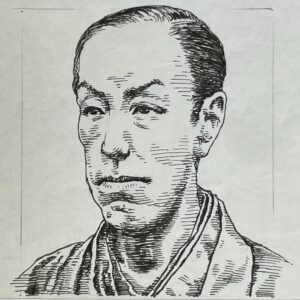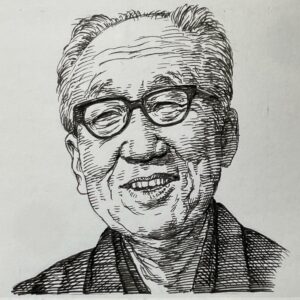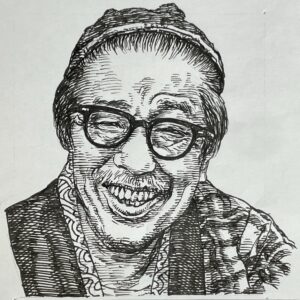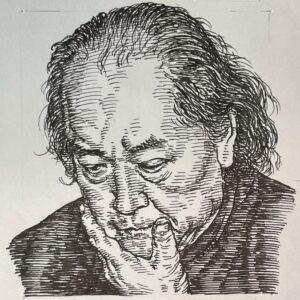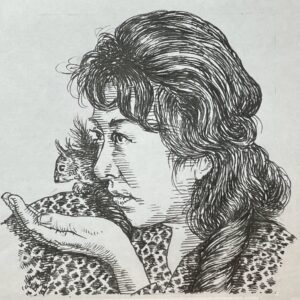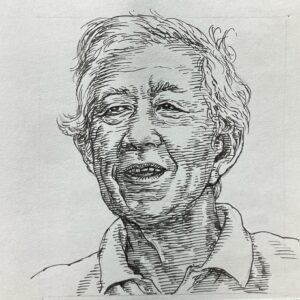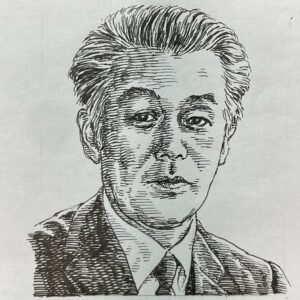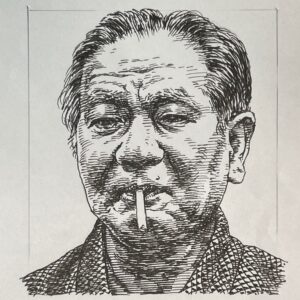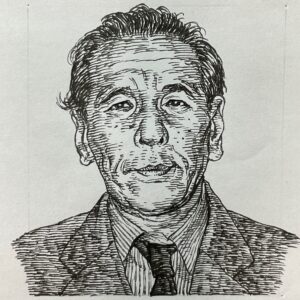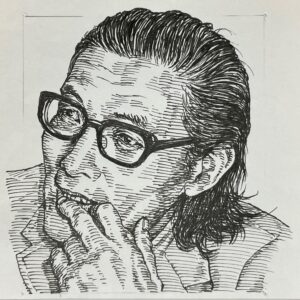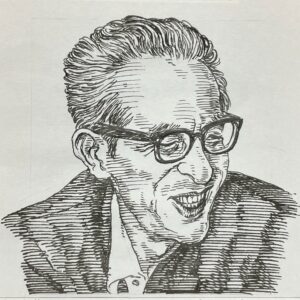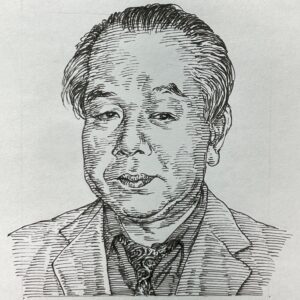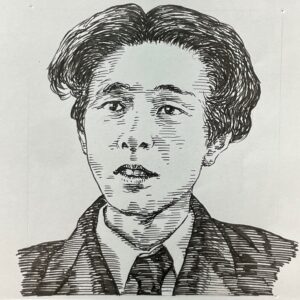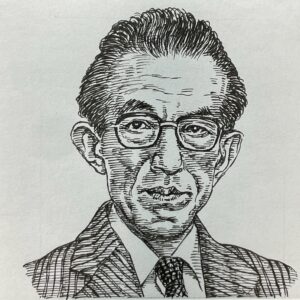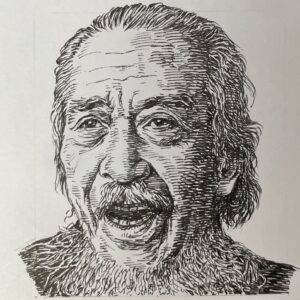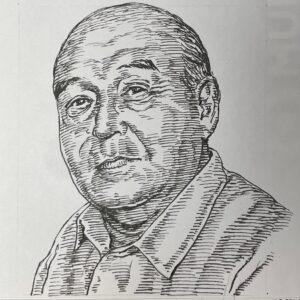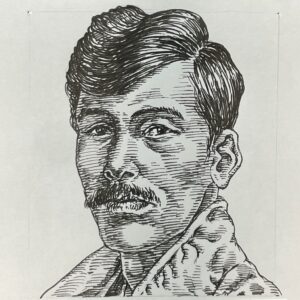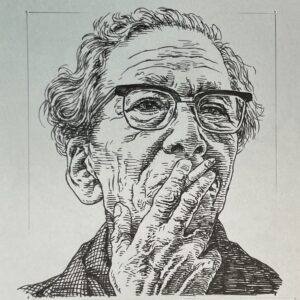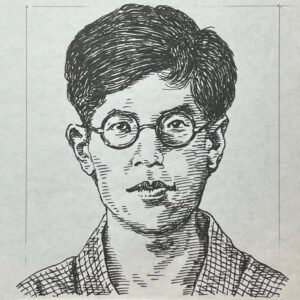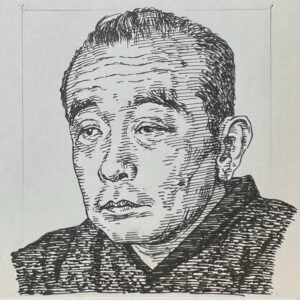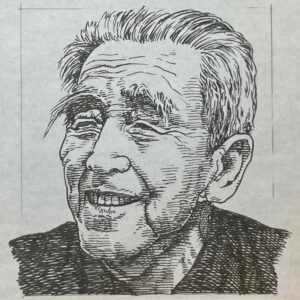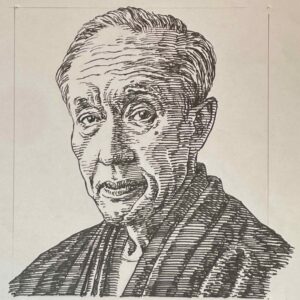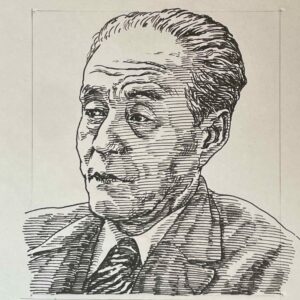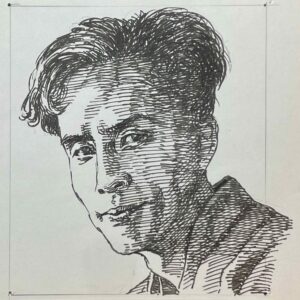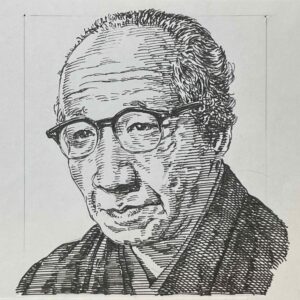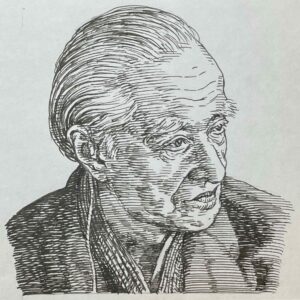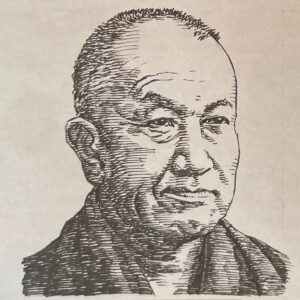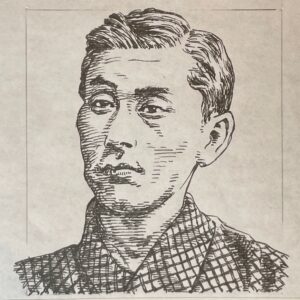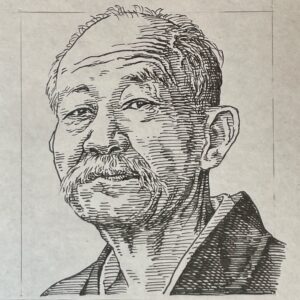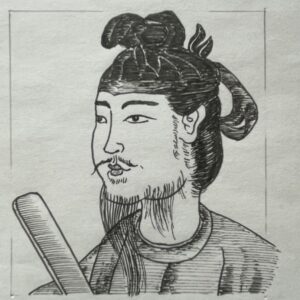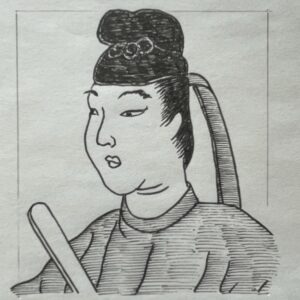東京都出身 From Tokyo
ようこそ!フリーイラストポートレートと
歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ
こちらのページでは出生都道府県別イラスト
ポートレートとして東京都出身の偉人たち を
お楽しみください
東京都出身イラストポートレート(Syusuke Galleryより )
東京都出身・新着偉人(It's New)
【文学の部屋|山上路夫】昭和時代編.232New!!
2026-02-16
【文学の部屋|横井 弘】昭和時代編.230New!!
2026-02-14
【文学の部屋|水木かおる】昭和時代編.229
2026-02-13
【文学の部屋|宮川哲夫】昭和時代編.226
2026-02-10
【文学の部屋|西沢 爽】昭和時代編.223
2026-02-07
【文学の部屋|佐伯孝夫】昭和時代編.216
2026-01-31
【文学の部屋|梶原一騎】昭和時代編.212
2026-01-25
【文学の部屋|川崎吉蔵】昭和時代編.211
2026-01-24
【文学の部屋|川崎隆章】昭和時代編.210
2026-01-23
【文学の部屋|永 六輔】昭和時代編.206
2026-01-17
【文学の部屋|都筑道夫】昭和時代編.202
2026-01-13
【文学の部屋|三木トリロー(鶏郎)】昭和時代編.198
2026-01-09
【文学の部屋|成島柳北】明治時代編.45
2026-01-01
【文学の部屋|加藤楸邨】昭和時代編.193
2025-12-31
【文学の部屋|サトウハチロー】昭和時代編.192
2025-12-30
【文学の部屋|蔵原惟人】昭和時代編.191
2025-12-29
【文学の部屋|長田幹彦】大正時代編.55
2025-12-27
【文学の部屋|江藤 淳】昭和時代編.185
2025-12-20
【文学の部屋|瀬木慎一】昭和時代編.183
2025-12-18
【文学の部屋|なだ いなだ】昭和時代編.178
2025-12-12
【文学の部屋|色川武大】昭和時代編.177
2025-12-11
【文学の部屋|吉原幸子】昭和時代編.176
2025-12-10
【文学の部屋|澤地久枝】昭和時代編.173
2025-12-07
【文学の部屋|大庭みな子】昭和時代編.172
2025-12-06
【文学の部屋|向田邦子】昭和時代編.171
2025-12-05
【文学の部屋|岸田衿子】昭和時代編.170
2025-12-04
【文学の部屋|高田敏子】昭和時代編.167
2025-12-01
【文学の部屋|白洲正子】昭和時代編.166
2025-11-30
【文学の部屋|斎藤 史】昭和時代編.165
2025-11-29
【文学の部屋|田中澄江】昭和時代編.164
2025-11-28
【文学の部屋|円地文子】昭和時代編.161
2025-11-25
【文学の部屋|森 茉莉】昭和時代編.155
2025-11-19
【文学の部屋|宮本百合子】昭和時代編.151
2025-11-15
【文学の部屋|柳原白蓮】大正時代編.51
2025-11-05
【文学の部屋|田村俊子】大正時代編.51
2025-11-04
【文学の部屋|長谷川時雨】明治時代編.44
2025-11-03
【文学の部屋|樋口一葉】明治時代編.43
2025-11-02
【文学の部屋|北 杜夫】昭和時代編.140
2025-10-28
【文学の部屋|いいだ もも】昭和時代編.138
2025-10-26
【文学の部屋|星 新一】昭和時代編.137
2025-10-25
【文学の部屋|山口 瞳】昭和時代編.136
2025-10-24
【文学の部屋|三島由紀夫】昭和時代編.135
2025-10-23
【文学の部屋|安部公房】昭和時代編.133
2025-10-21
【文学の部屋|池波正太郎】昭和時代編.132
2025-10-20
【文学の部屋|遠藤周作】昭和時代編.130
2025-10-18
【文学の部屋|田村隆一】昭和時代編.129
2025-10-17
【文学の部屋|中井英夫】昭和時代編.128
2025-10-16
【文学の部屋|有馬頼義】昭和時代編.123
2025-10-11
【文学の部屋|斎藤隆介】昭和時代編.120
2025-10-08
【文学の部屋|立原道造】昭和時代編.117
2025-10-05
【文学の部屋|福田恆存】昭和時代編.115
2025-10-03
【文学の部屋|中村光夫】昭和時代編.114
2025-10-02
【文学の部屋|植草甚一】昭和時代編.109
2025-09-27
【文学の部屋|中島健蔵】昭和時代編.100
2025-09-18
【文学の部屋|薩摩治郎八】昭和時代編.94
2025-09-12
【文学の部屋|青山二郎】昭和時代編.93
2025-09-11
【文学の部屋|土岐善麿】大正時代編.47
2025-08-28
【文学の部屋|高村光太郎】大正時代編.44
2025-08-25
【文学の部屋|加藤周一】昭和時代編.78
2025-08-14
【文学の部屋|木下順二】昭和時代編.73
2025-08-09
【文学の部屋|永井龍男】昭和時代編.69
2025-08-05
【文学の部屋|武田泰淳】昭和時代編.66
2025-08-02
【文学の部屋|吉田健一】昭和時代編.64
2025-07-31
【文学の部屋|大岡昇平】昭和時代編.60
2025-07-27
【文学の部屋|中島 敦】昭和時代編.59
2025-07-26
【文学の部屋|富田常雄】昭和時代編.47
2025-07-14
【文学の部屋|舟橋聖一】昭和時代編.46
2025-07-13
【文学の部屋|堀 辰雄】昭和時代編.44
2025-07-11
【文学の部屋|小林秀雄】昭和時代編.39
2025-07-06
【文学の部屋|村山知義】昭和時代編.32
2025-06-29
【文学の部屋|石川 淳】昭和時代編.25
2025-06-22
【文学の部屋|堀口大學】昭和時代編.12
2025-06-09
【文学の部屋|水原秋桜子】昭和時代編.11
2025-06-08
【文学の部屋|岸田國士】昭和時代編.8
2025-06-05
【文学の部屋|辰野 隆】昭和時代編.5
2025-06-02
【文学の部屋|長與善郎】大正時代編.42
2025-06-01
【文学の部屋|荻原井泉水】大正時代編.40
2025-05-30
【文学の部屋|西條八十】大正時代編.36
2025-05-26
【文学の部屋|芥川龍之介】大正時代編.35
2025-05-25
【文学の部屋|広津和郎】大正時代編.32
2025-05-22
【文学の部屋|久保田万太郎】大正時代編.30
2025-05-20
【文学の部屋|川路柳虹】大正時代編.28
2025-05-18
【文学の部屋|水上瀧太郎】大正時代編.27
2025-05-17
【文学の部屋|柳原白蓮】大正時代編.23
2025-05-13
【文学の部屋|中 勘助】大正時代編.22
2025-05-12
【文学の部屋|谷崎潤一郎】大正時代編.20
2025-05-10
【文学の部屋|永井荷風】大正時代編.15
2025-05-04
【文学の部屋|岡 鬼太郎】明治時代編.34
2025-04-30
【文学の部屋|岡本綺堂】明治時代編.33
2025-04-29
【文学の部屋|山田美妙】明治時代編.26
2025-04-22
【文学の部屋|岡本かの子】大正時代編.9
2025-04-12
【文学の部屋|吉井 勇】大正時代編.7
2025-04-10
【文学の部屋|武者小路実篤】大正時代編.5
2025-04-08
【文学の部屋|中里介山】大正時代編.4
2025-04-07
【文学の部屋|有島武郎】明治時代編.21
2025-04-01
【文学の部屋|上田 敏】明治時代編.19
2025-03-30
【文学の部屋|尾崎紅葉】明治時代編.8
2025-03-19
【文学の部屋|夏目漱石】明治時代編.6
2025-03-17
【文学の部屋|幸田露伴】明治時代編.5
2025-03-16
広告コーナー
いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により
運営させていただいております
皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます
いらすとすてーしょん検索コーナー
いらすとすてーしょん検索コーナー
いらすとすてーしょん検索コーナー
新着偉人(It's New)
新たに公開のイラストポートレートをご覧ください
【政治の部屋|聖徳太子(厩戸王)】飛鳥時代編.2New!!
2026-02-20
【政治の部屋|秦 河勝】飛鳥時代編.1
2026-02-19
1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓
2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です
2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします