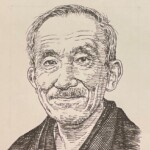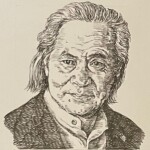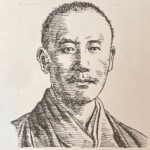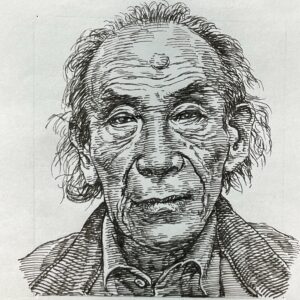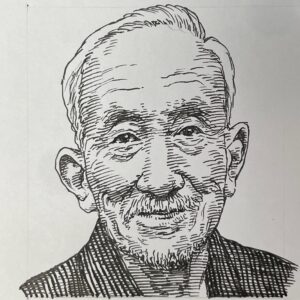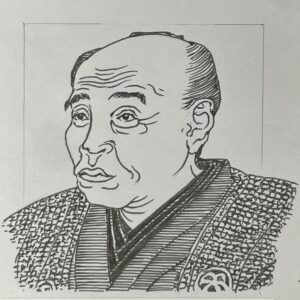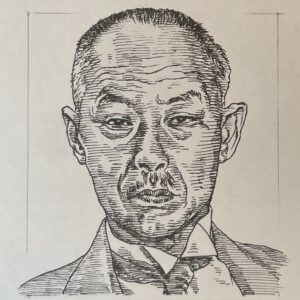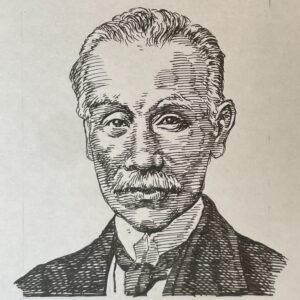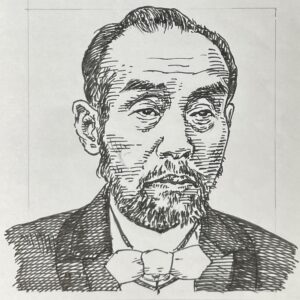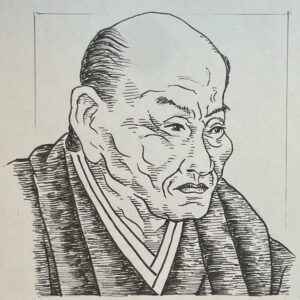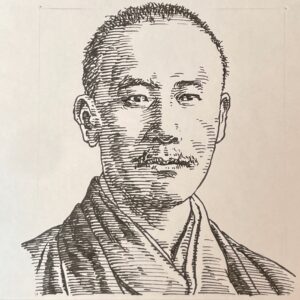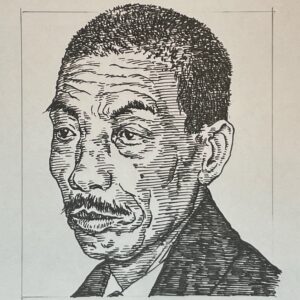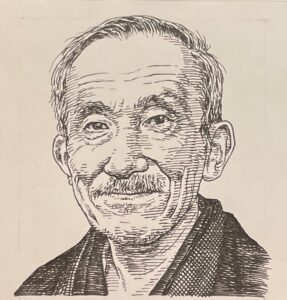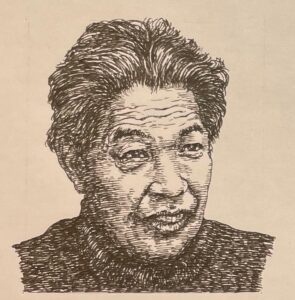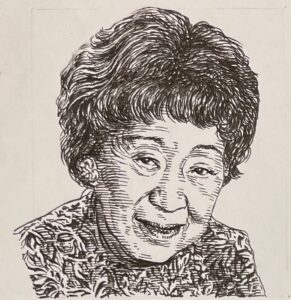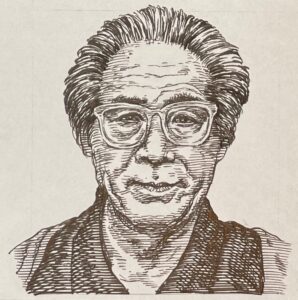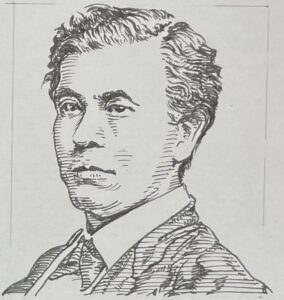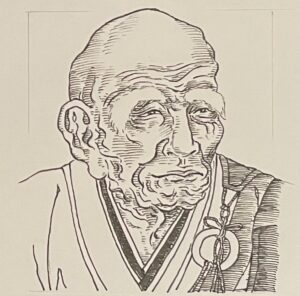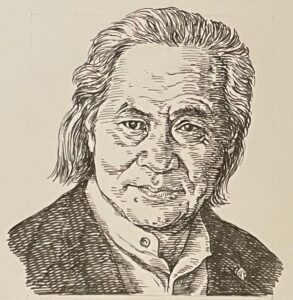山口県出身 From Yamaguchi
ようこそ!フリーイラストポートレートと
歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ
こちらのページでは出生都道府県別イラスト
ポートレートとして山口県出身の偉人たち を
お楽しみください
山口県出身イラストポートレート(Syusuke Galleryより)
山口県出身・新着偉人(It's New)
【文学の部屋|宇野千代】昭和時代編.150
2025-11-14
【文学の部屋|金子みすゞ】大正時代編.53
2025-11-07
【文学の部屋|まど みちお】昭和時代編.110
2025-09-28
【文学の部屋|新村 出】昭和時代編.83
2025-08-31
【文学の部屋|種田山頭火】大正時代編.43
2025-08-24
【文学の部屋|中原中也】昭和時代編.54
2025-07-21
【経営者の部屋|熊谷五一】江戸時代編.22
2025-01-12
【経営者の部屋|鮎川義介】大正時代編.7
2024-11-06
【経営者の部屋|瀧川辨三】明治時代編.29
2024-09-29
【経営者の部屋|藤田伝三郎】明治時代編.5
2024-09-05
【医学の部屋|斎藤方策】ビフォーアフターP.F.シーボルト編③
2024-04-16
【画家の部屋|松林桂月】南画、東の巨匠
2023-10-17
【画家の部屋|狩野芳崖】近代日本画の祖
2023-10-04
【経済学者の部屋|河上 肇】貧困問題に真っ向勝負
2023-03-14
【内閣総理大臣の部屋|佐藤榮作】第61・62・63代(通算在職日数2798日)
2023-02-11
【言語学の部屋|新村 出】偉大にしてチャーミングと推薦いただきました
2023-01-22
【民族学の部屋|宮本常一】日本を隅々まで歩いた学者
2023-01-16
【音楽の部屋|松島詩子】教師から転職「マロニエの木陰」大ヒット
2022-11-07
【陶芸家の部屋|坂田泥華(一平)13代】萩焼坂田泥華窯16代襲名が待ち焦がれる
2022-10-26
【文壇発見】「中原中也」朝ドラ「ちむどんどん」で再注目されました 文学の部屋
2022-08-08
【探求ネタ】「木戸孝允」日本史から見た偉人たち
2022-06-11
【探究ネタ】「桂庵玄樹」日本の宗教に携われた人々
2022-05-24
【医学の部屋|斎藤方策 Housaku Saito】漢蘭折衷医学のスペシャリスト
2022-05-22
【ファインダーの巨匠|林 忠彦】文壇を輝かせた男 写真家の部屋
2022-04-28
広告コーナー
いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により
運営させていただいております
皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます
いらすとすてーしょん検索コーナー
いらすとすてーしょん検索コーナー
いらすとすてーしょん検索コーナー
新着偉人(It's New)
新たに公開のイラストポートレートをご覧ください
【文学の部屋|深田久弥】昭和時代編.209New!!
2026-01-22
【文学の部屋|高頭仁兵衛】明治時代編.49
2026-01-21
1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓
2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です
2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします