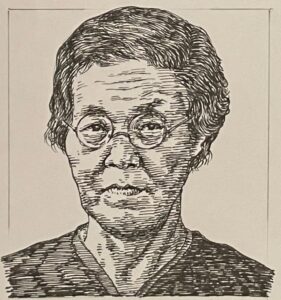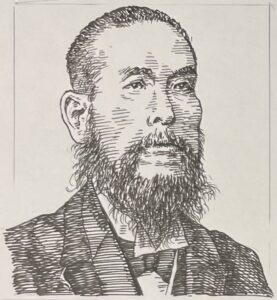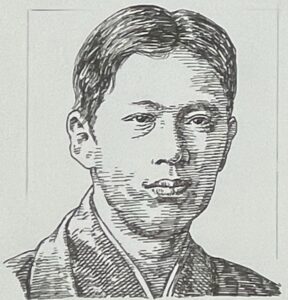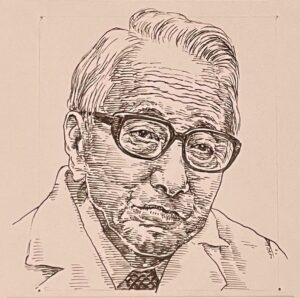長野県出身 From Nagano
ようこそ!フリーイラストポートレートと
歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ
こちらのページでは出生都道府県別イラスト
ポートレートとして長野県出身の偉人たち を
お楽しみください
長野県出身イラストポートレート(Syusuke Galleryより)
長野県出身・新着偉人(It's New)
【文学の部屋|平林たい子】昭和時代編.160
2025-11-24
【文学の部屋|土屋隆夫】昭和時代編.121
2025-10-09
【文学の部屋|日夏耿之介】昭和時代編.89
2025-09-07
【文学の部屋|河竹繁俊】昭和時代編.85
2025-09-02
【文学の部屋|窪田空穂】明治時代編.40
2025-08-22
【文学の部屋|新田次郎】昭和時代編.68
2025-08-04
【文学の部屋|臼井吉見】昭和時代編.51
2025-07-18
【文学の部屋|島木赤彦】大正時代編.13
2025-05-02
【文学の部屋|木下尚江】明治時代編.10
2025-03-21
【文学の部屋|小林一茶】江戸時代編.20
2025-02-28
【文学の部屋|大島蓼太】江戸時代編.10
2025-02-17
【経営者の部屋|小尾俊人】昭和時代編.37
2025-01-06
【経営者の部屋|五島慶太】大正時代編.8
2024-11-07
【経営者の部屋|小山松寿】明治時代編.58
2024-10-28
【経営者の部屋|藤原銀次郎】明治時代編.53
2024-10-23
【江戸文学|俳諧の連歌】「大島蓼太」門人の数は数千人!?
2023-04-04
【文学の部屋|竹内 好】弱いものイジメと戦う文学者
2023-01-18
【民族学の部屋|岡 正雄】日本民族の祖は5つからなる!?
2023-01-15
【江戸文学|俳諧の連歌】「小林一茶」親しみある作品はなんと2万句
2022-12-20
【医学の部屋|竹内茂代】東京女子医科大学1期生は初の女性衆議院議員
2022-11-19
【植物学者の部屋|河野齢蔵】高山植物研究の第一人者は校長先生!?
2022-10-07
【画家の部屋|菱田春草】反戦のオモイは「寡婦と孤児」
2022-05-15
【医学の部屋|丸山千里】30年経った丸山ワクチンはいま
2022-04-25
広告コーナー
いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により
運営させていただいております
皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます
いらすとすてーしょん検索コーナー
いらすとすてーしょん検索コーナー
いらすとすてーしょん検索コーナー
新着偉人(It's New)
新たに公開のイラストポートレートをご覧ください
【文学の部屋|深田久弥】昭和時代編.209New!!
2026-01-22
【文学の部屋|高頭仁兵衛】明治時代編.49
2026-01-21
1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓
2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です
2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします


jpeg/3373805679.jpeg)










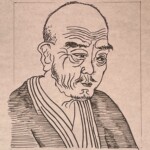





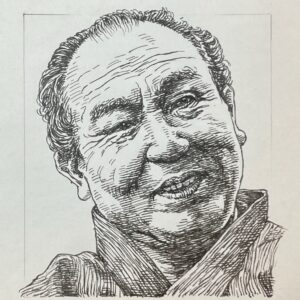
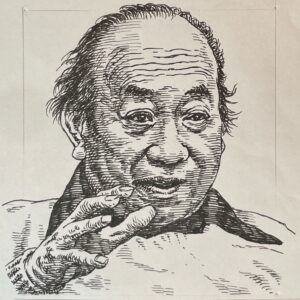
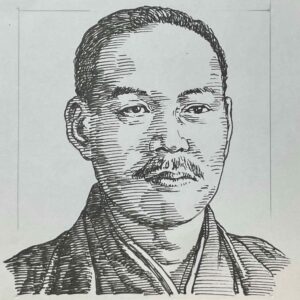
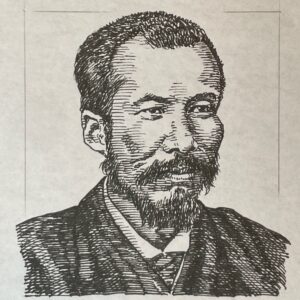
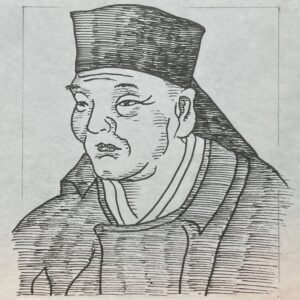
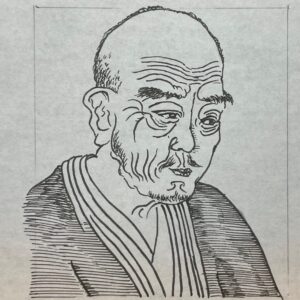
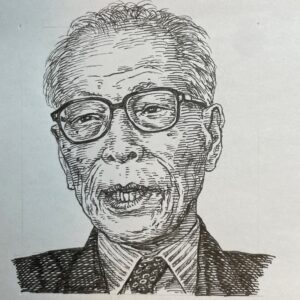



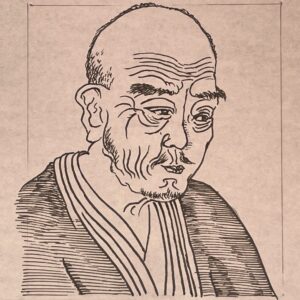
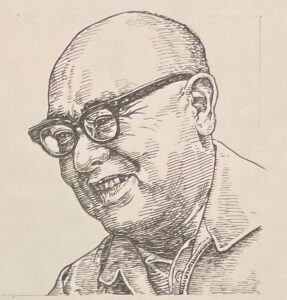

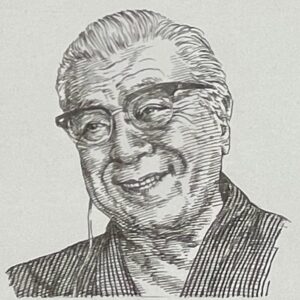
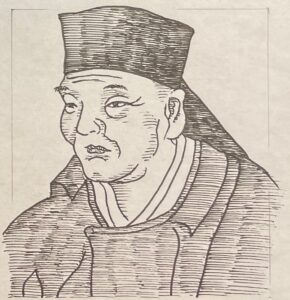
jpeg-300x294.jpeg)