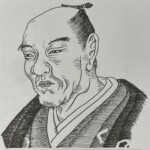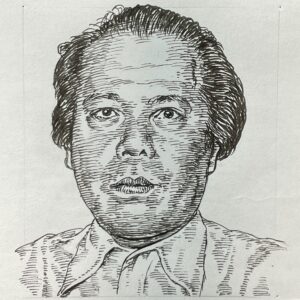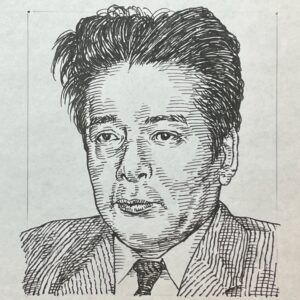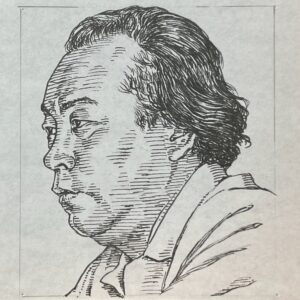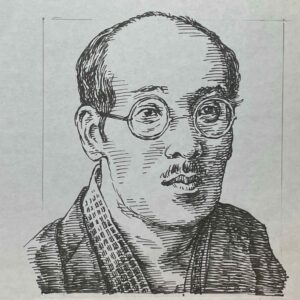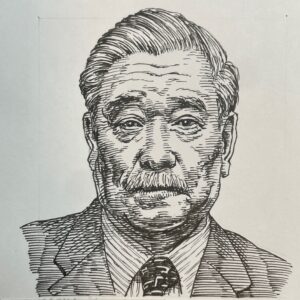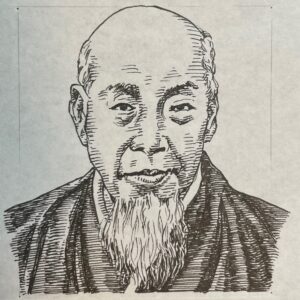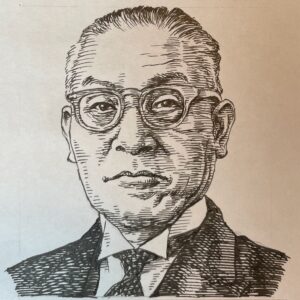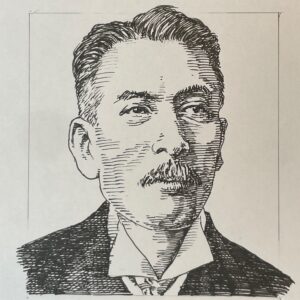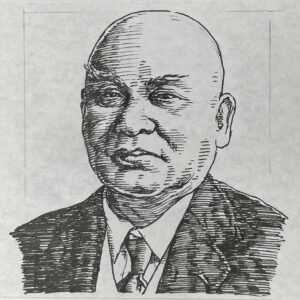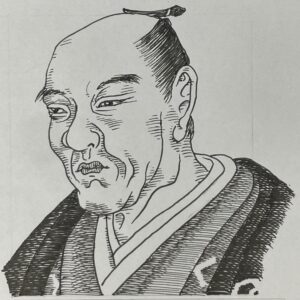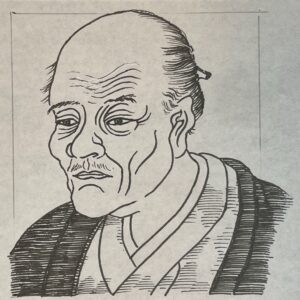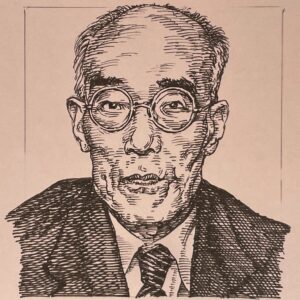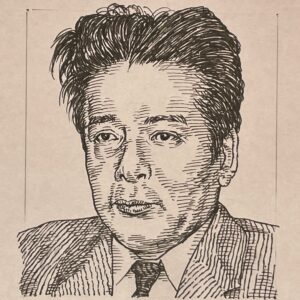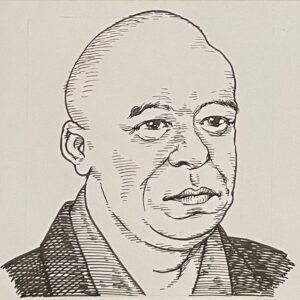福岡県出身 From Fukuoka
ようこそ!フリーイラストポートレートと
歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ
こちらのページでは出生都道府県別イラスト
ポートレートとして福岡県出身の偉人たち を
お楽しみください
福岡県出身イラストポートレート(Syusuke Galleryより )
福岡県出身・新着偉人(It's New)
【文学の部屋|つかこうへい】昭和時代編.190
2025-12-25
【文学の部屋|林 芙美子】昭和時代編.156
2025-11-20
【文学の部屋|福永武彦】昭和時代編.122
2025-10-10
【文学の部屋|梅崎春生】昭和時代編.119
2025-10-07
【文学の部屋|与田凖一】昭和時代編.105
2025-09-23
【文学の部屋|豊島与志雄】昭和時代編.86
2025-09-03
【文学の部屋|小宮豊隆】大正時代編.45
2025-08-26
【文学の部屋|末松謙澄】明治時代編.37
2025-08-19
【文学の部屋|花田清輝】昭和時代編.58
2025-07-25
【文学の部屋|火野葦平】昭和時代編.55
2025-07-22
【文学の部屋|葉山嘉樹】大正時代編.38
2025-05-28
【文学の部屋|宇野浩二】大正時代編.33
2025-05-23
【文学の部屋|夢野久作】昭和時代編.3
2025-04-18
【文学の部屋|大隈言道】江戸時代編.28
2025-03-08
【経営者の部屋|花村仁八郎】昭和時代編.42
2025-01-11
【経営者の部屋|田中久重】明治時代編.75
2025-01-04
【経営者の部屋|吉田秀雄】昭和時代編.15
2024-11-27
【経営者の部屋|太田清蔵 (5代目)】昭和時代編.9
2024-11-21
【経営者の部屋|石橋正二郎】大正時代編.13
2024-11-12
【経営者の部屋|團 琢磨】明治時代編.33
2024-10-03
【経営者の部屋|麻生太吉】明治時代編.9
2024-09-09
【経営者の部屋|神屋宗湛】室町・桃山時代編.1
2024-08-30
【経営者の部屋|林田正助】江戸時代編.4
2024-08-13
【物理学者の部屋|武谷三男】原子力平和利用を提唱
2023-07-11
【文学の部屋|北原白秋】「明星」の新人賞
2023-05-29
【文学の部屋|宇野浩二】唯美からリアリストへ
2023-05-24
【文学の部屋|花田清輝】レトリックの魔術師
2023-05-17
【文学の部屋|葉山嘉樹】プロレタリア文学をリードした一人
2023-05-16
【経営者の部屋|神屋宗湛】秀吉に寵愛された博多豪商
2023-03-23
【文壇発見|林芙美子】時代と感性をペンで綴る小説家
2023-02-13
広告コーナー
いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により
運営させていただいております
皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます
いらすとすてーしょん検索コーナー
いらすとすてーしょん検索コーナー
いらすとすてーしょん検索コーナー
新着偉人(It's New)
新たに公開のイラストポートレートをご覧ください
【文学の部屋|橘 樸】昭和時代編.194New!!
2026-01-05
【文学の部屋|桐生悠々】大正時代編.57
2026-01-04
1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓
2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です
2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします