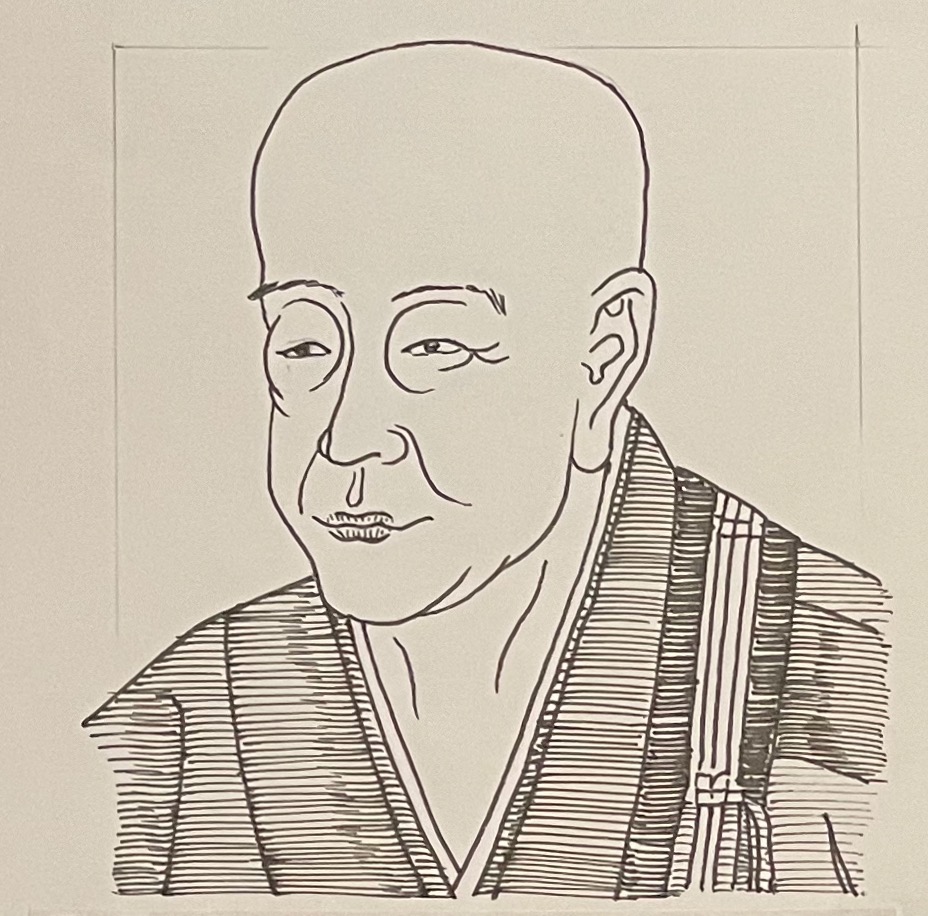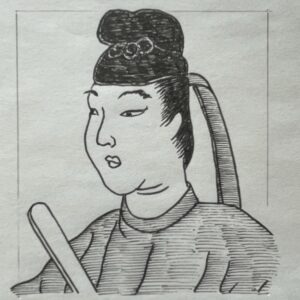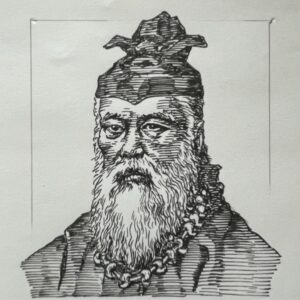林 羅山 Razan Hayashi
ようこそ!フリーイラストポートレートと歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ
こちらのページでは
①林 羅山イラストポートレート (Syusuke Galleryより)
①〜⑦のコンテンツをお届けさせていただきます
どうぞ【儒学・朱子学|林 羅山 Razan Hayashi】日本朱子学の祖 をお楽しみください
林 羅山イラストポートレート(Syusuke Galleryより)
日本朱子学 林 羅山を祖とする系統

師の薦めにより徳川家康より4代家綱まで将軍に仕え侍講(君主の学問教育)となる
林 羅山に会える場所
国指定史跡「林氏墓地」
National Historic Monument「Hayashi's cemetery」
東京都新宿区市谷山伏町16番地
東京都新宿区教育委員会 案内板より
江戸時代、朱子学をもって徳川家康に仕えた林羅山とその子孫・一族の墓所で、国の史跡に指定されている。
朱子学は、孔子の教えを基にした儒学の中の一派であり、林羅山が徳川家康に登用され、朱子学を講じるなど、幕府は朱子学を重視した。林家は朱子学を武家の子孫に教授するため上野忍ヶ岡の別邸内に家塾を開き、講師をまつる聖堂を建てた。
この家塾は、五代将軍徳川綱吉の時に湯島に移され、各z通されて昌平黌と呼ばれ、林述斎(八世)の時には幕府直轄の学問所となった(昌平坂学問所ともいう)。
林家は、当主が代々大学頭などに任ぜられ、学問・法制・外交などの分野で手腕を振るった。
この墓地は、元禄十一年(一六九八)鳳岡(三世)の時に拝領した屋敷の一部に造営されたものである。次第に粛宗されたため、往時の様相は失われているが、八世から十一世までの当主の墓四基は、めずらしい儒葬の様式をとどめた貴重なものである。
毎年十一月初旬の文化財保護強調週間には、墓地の一般公開を行なっています
※一般公開情報は新宿区立新宿歴史博物館公式HPをご確認ください
参考まで 2022年の公開情報はこちらです
【公 開 日】11月3日(木祝)・5日(土)・6日(日)(雨天決行・荒天中止)
【 時 間 】10:00~15:00
【 会 場 】国史跡林氏墓地(市谷山伏町1-15)
都営地下鉄大江戸線「牛込柳町駅」から徒歩約5分
【 料 金 】無料
【申 込 み】不要。当日直接会場へ。
【そ の 他】新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、ボランティアによる解説は行いません。
【問 合 せ】新宿歴史博物館 03-3359-2131
4.jpeg)
武士の最高学府「昌平坂学問所」学長・林述斎
学び始めはここ建仁寺でした
11~12歳のころ、栄西禅師によって開山された建仁寺にて仏教を学ぶ
儒学 国学・新着偉人(It's New)はこちらから
- 【国学者|本居宣長 Norinaga Motoori】化政期の国学四大人(こくがくしうし)の一人
- 【国学者|荷田春満 Azumamaro Kadano】化政期の国学四大人(こくがくしうし)の一人
- 【国学者|賀茂真淵 Mabuchi Kamono】化政期の国学四大人(こくがくしうし)の一人
- 【儒学・朱子学|林 羅山 Razan Hayashi】日本朱子学の祖
- 【儒学・京学派|藤原惺窩 Seika Fujiwara】京学派(日本儒学)の祖
- 【儒学・古学|山鹿素行 Soko Yamaga】古学の祖
- 【儒学・陽明学|中江藤樹 Tozyu Nakae】日本陽明学の祖
- 【国学者|平田篤胤 Atsutane Hirata】化政期の国学四大人(こくがくしうし)の一人
- 【儒学・朱子学|林 述斎 Jyusai Hayashi】武士の最高学府「昌平坂学問所」学長
- 【儒学・折衷学派|細井平洲】藩士のみならず町民にも説く教育者
広告コーナー
いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により
運営させていただいております
皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます
いらすとすてーしょん検索コーナー
いらすとすてーしょん検索コーナー
新着偉人(It's New)
新たに公開のイラストポートレートをご覧ください
【政治の部屋|秦 河勝】飛鳥時代編.1New!!
【政治の部屋|武内宿禰】古墳時代編.2
1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓
2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です
2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします