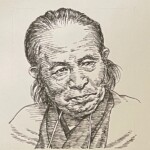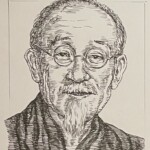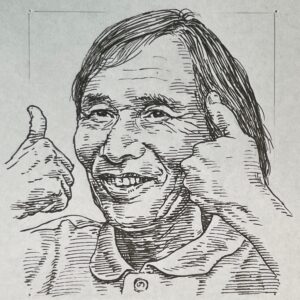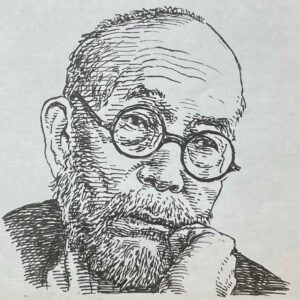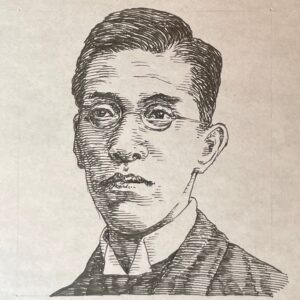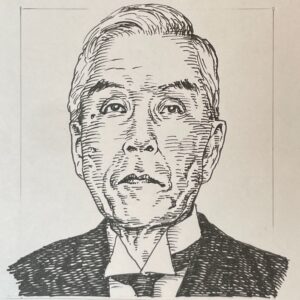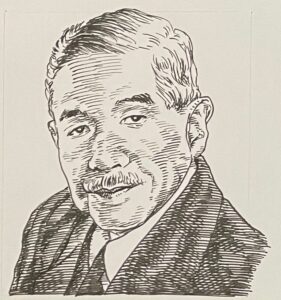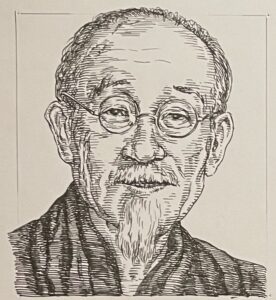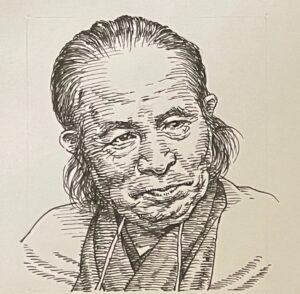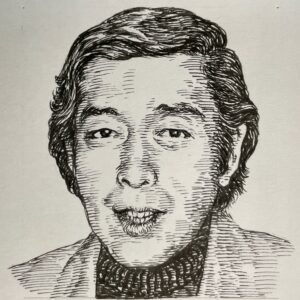山形県出身 From Yamagata
ようこそ!フリーイラストポートレートと
歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ
こちらのページでは出生都道府県別イラスト
ポートレートとして山形県出身の偉人たち を
お楽しみください
山形県出身イラストポートレート(Syusuke Galleryより )
山形県出身・新着偉人(It's New)
【文学の部屋|井上ひさし】昭和時代編.204
2026-01-15
【文学の部屋|藤沢周平】昭和時代編.141
2025-10-29
【文学の部屋|吉野 弘】昭和時代編.139
2025-10-27
【文学の部屋|斎藤茂吉】大正時代編.19
2025-05-08
【文学の部屋|浜田広介】大正時代編.11
2025-04-14
【文学の部屋|高山樗牛】明治時代編.13
2025-03-24
【経営者の部屋|池田成彬】明治時代編.49
2024-10-19
【建築家の部屋|佐野利器】いまでは当たり前の耐震構造を始めて提唱した建築家
2022-09-19
【建築家の部屋|伊東忠太】築地本願寺設計した建築家は日本建築史の祖
2022-09-17
【ファインダーの巨匠|土門 拳】 私のレンズで真実の底まで暴く
2022-04-20
広告コーナー
いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により
運営させていただいております
皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます
いらすとすてーしょん検索コーナー
いらすとすてーしょん検索コーナー
いらすとすてーしょん検索コーナー
新着偉人(It's New)
新たに公開のイラストポートレートをご覧ください
【文学の部屋|山上路夫】昭和時代編.232New!!
2026-02-16
【文学の部屋|水島 哲】昭和時代編.231
2026-02-15
1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓
2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です
2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします