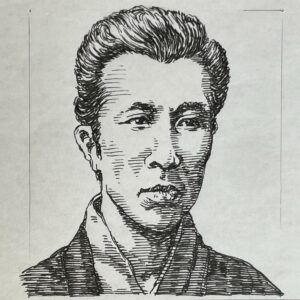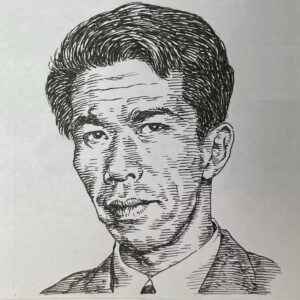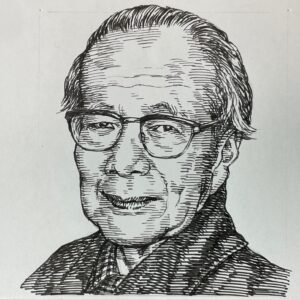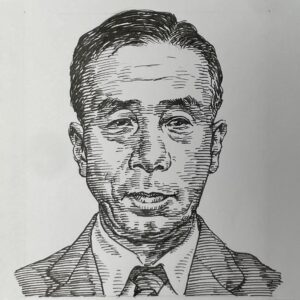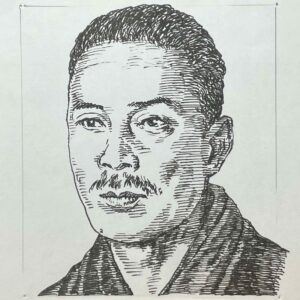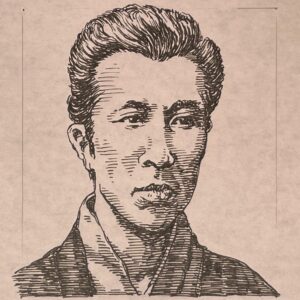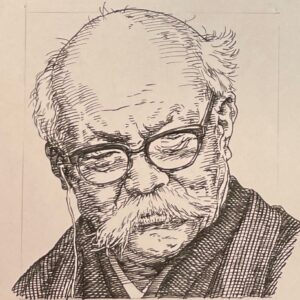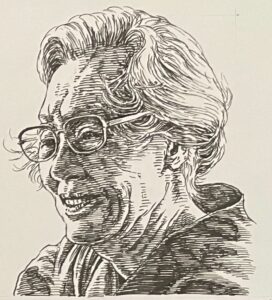長崎県出身 From Nagasaki
ようこそ!フリーイラストポートレートと
歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ
こちらのページでは出生都道府県別イラスト
ポートレートとして長崎県出身の偉人たち を
お楽しみください
長崎県出身イラストポートレート(Syusuke Galleryより)
長崎県出身・新着偉人(It's New)
【文学の部屋|半井桃水】明治時代編.46
2026-01-02
【文学の部屋|佐多稲子】昭和時代編.159
2025-11-23
【文学の部屋|山本健吉】昭和時代編.108
2025-09-26
【文学の部屋|伊東静雄】昭和時代編.106
2025-09-24
【文学の部屋|田中千禾夫】昭和時代編.102
2025-09-20
【文学の部屋|河上徹太郎】昭和時代編.97
2025-09-15
【文学の部屋|広津柳浪】明治時代編.24
2025-04-20
【文学の部屋|福地桜痴(源一郎)】明治時代編.1
2025-03-12
【経営者の部屋|三浦甲子二】昭和時代編.41
2025-01-10
【経営者の部屋|松永安左エ門】大正時代編.1
2024-10-31
【経営者の部屋|大浦 慶】江戸時代編.18
2024-08-27
【医学の部屋|楠本たき】ビフォーアフターP.F.シーボルト編⑥
2024-04-19
【物理学者の部屋|長岡半太郎】初代大阪帝国大学総長
2023-07-07
【ジャーナリストの部屋|半井桃水】弟子は樋口一葉
2023-04-23
【文壇発見】「佐多稲子」8月9日11時2分、今日読みたい1冊・樹影 文学の部屋
2022-08-09
広告コーナー
いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により
運営させていただいております
皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます
いらすとすてーしょん検索コーナー
いらすとすてーしょん検索コーナー
いらすとすてーしょん検索コーナー
新着偉人(It's New)
新たに公開のイラストポートレートをご覧ください
【文学の部屋|深田久弥】昭和時代編.209New!!
2026-01-22
【文学の部屋|高頭仁兵衛】明治時代編.49
2026-01-21
1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓
2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です
2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします