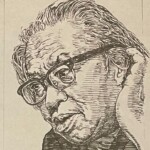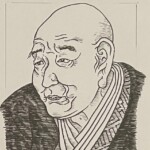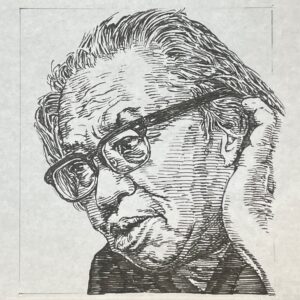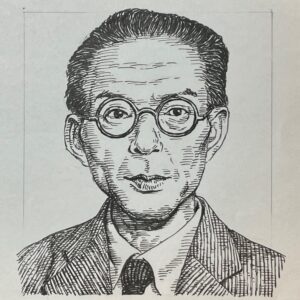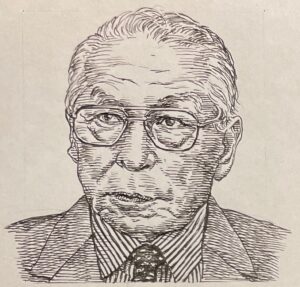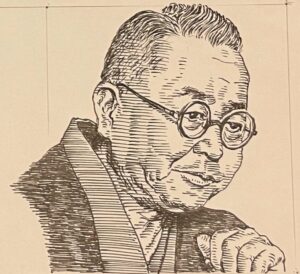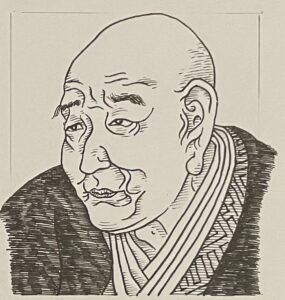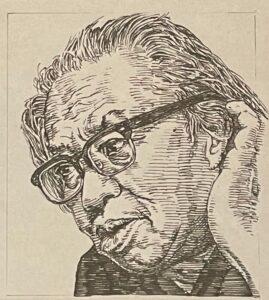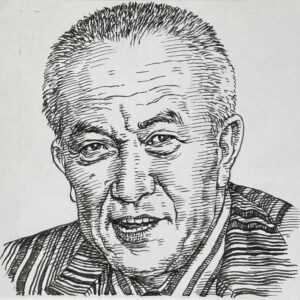広島県出身 From Hiroshima
ようこそ!フリーイラストポートレートと
歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ
こちらのページでは出生都道府県別イラスト
ポートレートとして広島県出身の偉人たち を
お楽しみください
広島県出身イラストポートレート(Syusuke Galleryより)
広島県出身・新着偉人(It's New)
【文学の部屋|大田洋子】昭和時代編.158
2025-11-22
【文学の部屋|阿川弘之】昭和時代編.81
2025-08-17
【文学の部屋|松本清張】昭和時代編.61
2025-07-28
【文学の部屋|原 民喜】昭和時代編.50
2025-07-17
【文学の部屋|井伏鱒二】昭和時代編.21
2025-06-18
【文学の部屋|鈴木三重吉】大正時代編.18
2025-05-07
【文学の部屋|小山内 薫】大正時代編.16
2025-05-05
【文学の部屋|倉田百三】大正時代編.10
2025-04-13
【文学の部屋|菅 茶山】江戸時代編.17
2025-02-24
【文学の部屋|小野 篁】平安時代編.3
2025-01-21
Oly / Para Memorial③ 織田幹雄
2024-07-27
【文学の部屋|小野 篁】閻魔庁にも仕えた文才
2023-09-16
【音楽の部屋|二葉あき子】人柄宿る歌声
2023-09-10
【発見アスリート|長沼 健 】元祖!サムライブルーを創った男
2022-12-05
【文壇発見】「井伏鱒二」8月6日8時15分今日読みたい1冊・黒い雨 文学の部屋
2022-08-06
【医学の部屋|土生玄碩 Genseki Habu】日本眼科医の祖
2022-05-21
【文壇発見】「松本清張」没後30年もドラマの定番 文学の部屋
2022-05-14
広告コーナー
いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により
運営させていただいております
皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます
いらすとすてーしょん検索コーナー
いらすとすてーしょん検索コーナー
いらすとすてーしょん検索コーナー
新着偉人(It's New)
新たに公開のイラストポートレートをご覧ください
【文学の部屋|永 六輔】昭和時代編.206New!!
2026-01-17
【文学の部屋|大江健三郎】昭和時代編.205
2026-01-16
1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓
2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です
2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします