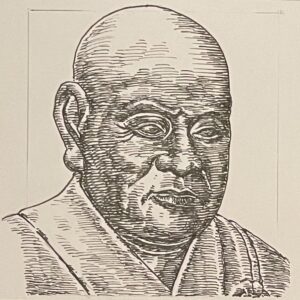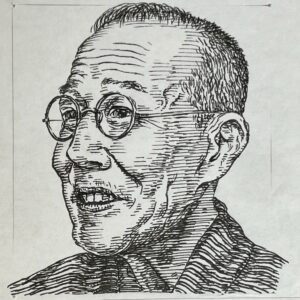福井県出身 From Fukui
ようこそ!フリーイラストポートレートと
歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ
こちらのページでは出生都道府県別イラスト
ポートレートとして福井県出身の偉人たち を
お楽しみください
福井県出身イラストポートレート(Syusuke Galleryより )
福井県出身・新着偉人(It's New)
【文学の部屋|水上 勉】昭和時代編.79
2025-08-15
【文学の部屋|中野重治】昭和時代編.35
2025-07-02
【文学の部屋|近松門左衛門】江戸時代編.5
2025-02-12
【江戸文学|浄瑠璃・歌舞伎】「近松門左衛門」今も人気曽根崎心中
2023-04-01
【探究ネタ】「朝倉義景」 103年の歴史を閉じた男 日本史からみた偉人たち
2022-07-29
【探究ネタ】「朝倉孝景」 103年の歴史を築いた男 日本史からみた偉人たち
2022-07-28
【探究ネタ】「泰澄」日本の宗教に携われた人々
2022-05-26
広告コーナー
いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により
運営させていただいております
皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます
いらすとすてーしょん検索コーナー
いらすとすてーしょん検索コーナー
いらすとすてーしょん検索コーナー
新着偉人(It's New)
新たに公開のイラストポートレートをご覧ください
【文学の部屋|花森安治】昭和時代編.196New!!
2026-01-07
【文学の部屋|平山蘆江】昭和時代編.195
2026-01-06
1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓
2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です
2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします

/2075165932.jpeg)
/4181912945.jpeg)





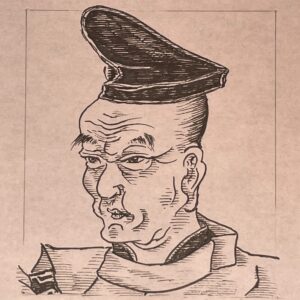
-292x300.jpeg)
-300x296.jpeg)