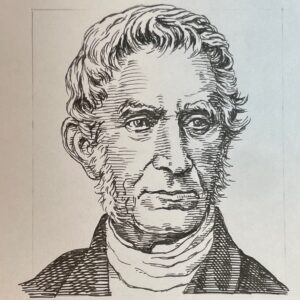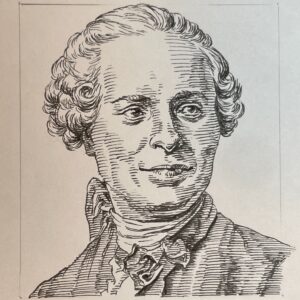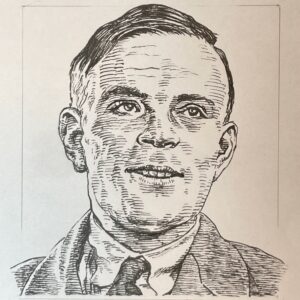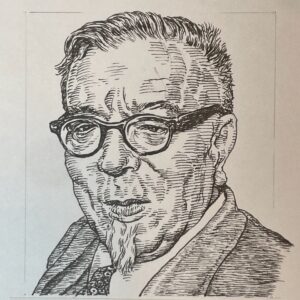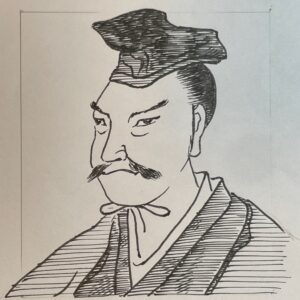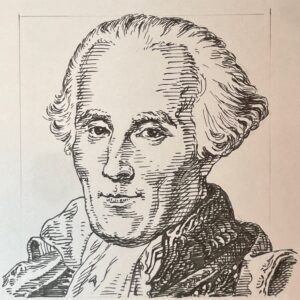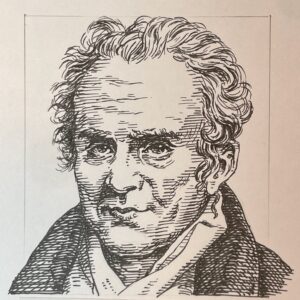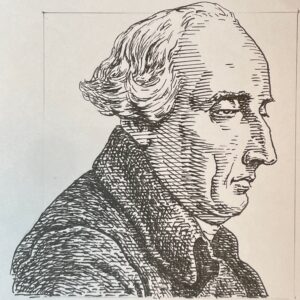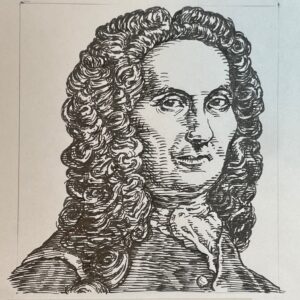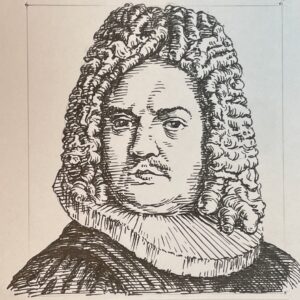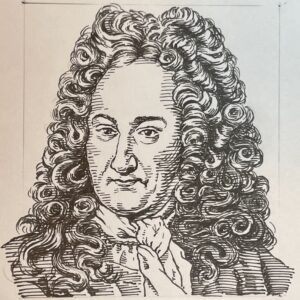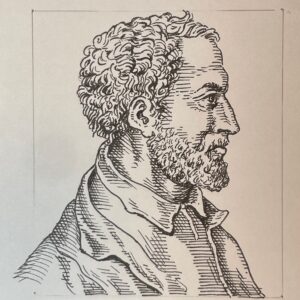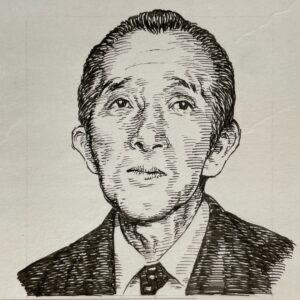カール・ワイエルシュトラス Karl Weierstrass
ようこそ!フリーイラストポートレートと
歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ
こちらのページでは【数学者の部屋|
ワイエルシュトラス】無学位の大教授
をお楽しみください
ワイエルシュトラス
イラストポートレート(Syusuke Galleryより)
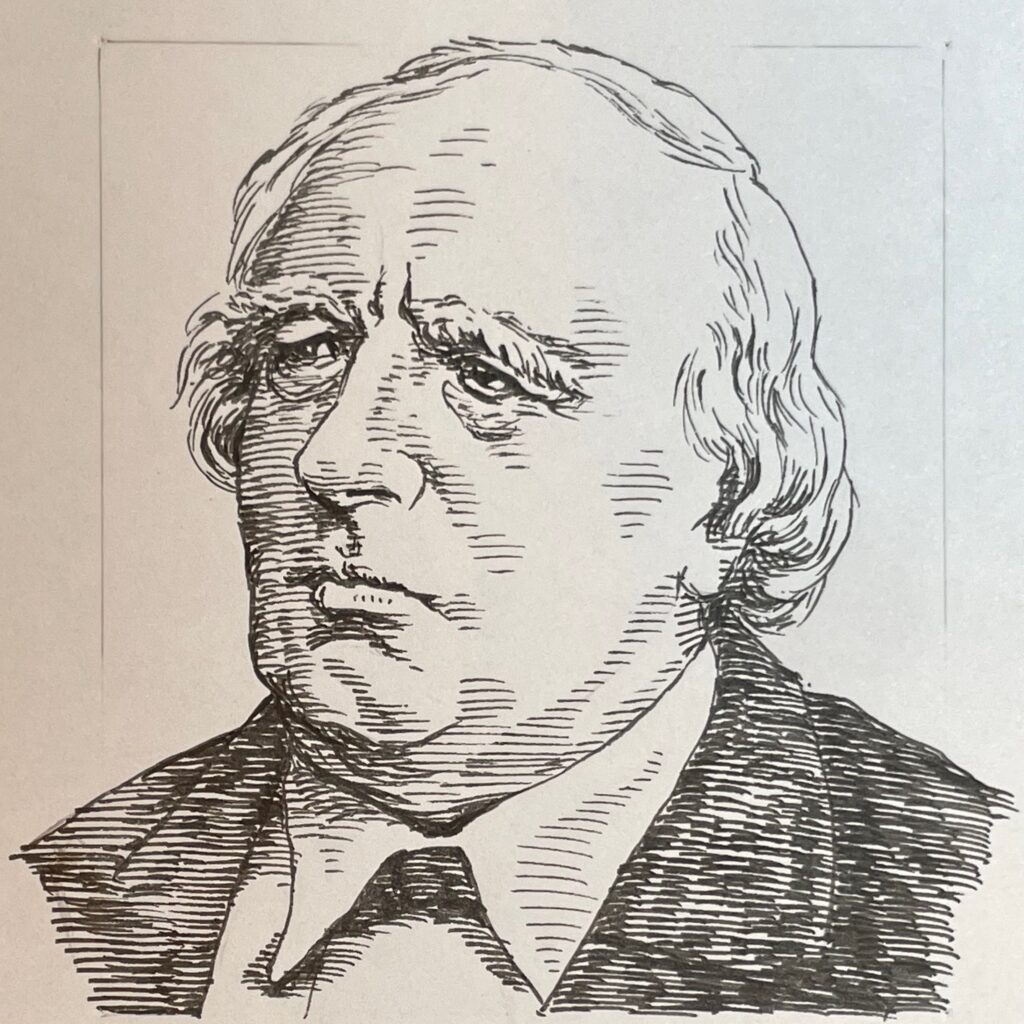
ドイツ出身 1815-1897
Gudermann(1798-1852)の講義により楕円関数に影響を受ける
関数要素・解析接続の概念を導入し解析関数を定義して解析関数論を樹立
またこの解析関数論からノルウェーの数学者アベールの生み出した
アベール関数をさらに研究し応用
数学者・新着偉人
(It's New)はこちらから
【数学者の部屋|ケトレー】BMIを提唱した統計学者
2023-08-18
【数学者の部屋|ダランベール】博識の方程式
2023-08-16
【数学者の部屋|チューリング】終戦へ導く暗号読解
2023-08-15
【数学者の部屋|マハラノビス】世界が尊敬する統計学者
2023-08-14
【数学者の部屋|ウィーナー】人と機会を繋ぐ巨人
2023-08-13
【数学者の部屋|関 孝和】世界に通用した和算の先駆者
2023-08-12
【数学者の部屋|アーベル】永遠に息づく代数学の解
2023-08-11
【数学者の部屋|ラプラス】謎解きの天才
2023-08-10
【数学者の部屋|モンジュ】平面に空間を描く天才
2023-08-09
【数学者の部屋|ラグランジュ】数学で新たな力学を導く
2023-08-08
【数学者の部屋|モアブル】発展させた確率論
2023-08-07
【数学者の部屋|ベルヌーイ】確率論を導くパイオニア
2023-08-06
【数学者の部屋|ライプニッツ】天才を超えた天才
2023-08-05
【数学者の部屋|フェルマー】350年も解けなかった問題の提起者
2023-08-04
【数学者の部屋|カルダーノ】確率論からギャンブルを説いた男
2023-08-03
【数学者の部屋|フィボナッチ】西洋にアラビア数字を導入した男
2023-08-02
広告コーナー
いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により
運営させていただいております
皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます
いらすとすてーしょん検索コーナー
いらすとすてーしょん検索コーナー
いらすとすてーしょん検索コーナー
新着偉人(It's New)
新たに公開のイラストポートレートをご覧ください
【文学の部屋|門田ゆたか】昭和時代編.219New!!
2026-02-03
【文学の部屋|野村俊夫】昭和時代編.218
2026-02-02
1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓
2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です
2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします