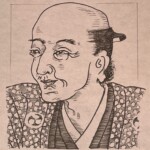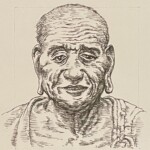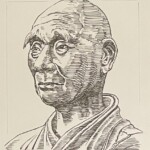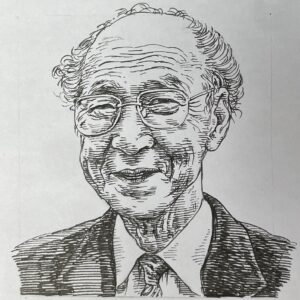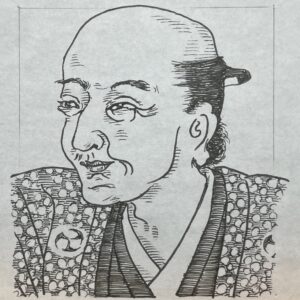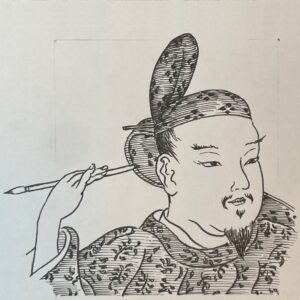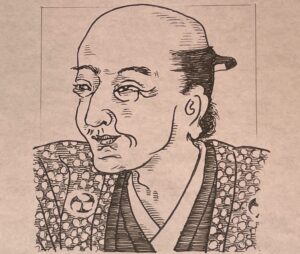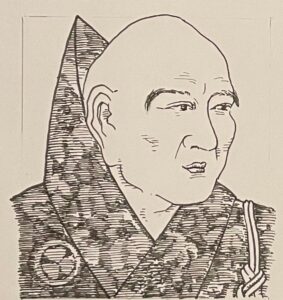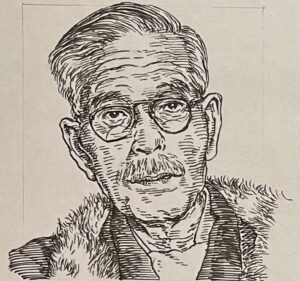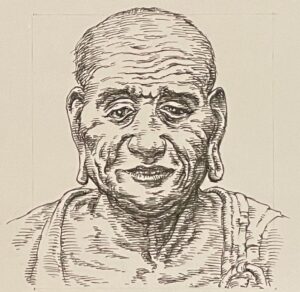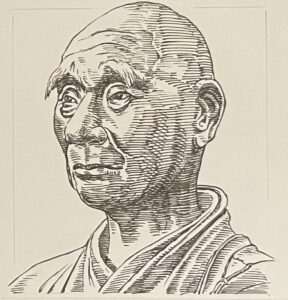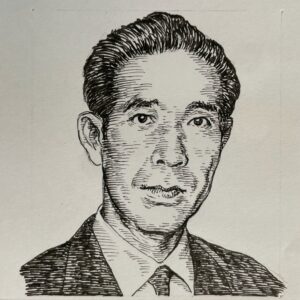奈良県出身 From Nara
ようこそ!フリーイラストポートレートと
歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ
こちらのページでは出生都道府県別イラスト
ポートレートとして奈良県出身の偉人たち を
お楽しみください
奈良県出身イラストポートレート(Syusuke Galleryより )
奈良県出身・新着偉人(It's New)
【文学の部屋|住井すゑ】昭和時代編.154
2025-11-18
【文学の部屋|中川正文】昭和時代編.127
2025-10-15
【文学の部屋|保田與重郎】昭和時代編.113
2025-10-01
【文学の部屋|池西言水】江戸時代編.4
2025-02-11
【文学の部屋|在原業平】平安時代編.2
2025-01-20
【経営者の部屋|茂木重次郎】明治時代編.70
2024-12-29
【文学の部屋|在原業平】伊勢物語で伝説化!?
2023-09-15
【化学者の部屋|福井謙一】日本初の化学賞受賞
2023-07-20
【江戸文学|俳諧の連歌】「池西言水」京都俳句のドン
2023-03-31
【探究ネタ】「隆光」日本の宗教に携われた人々
2022-11-16
【陶芸家の部屋|富本憲吉】模様から模様をつくるべからず!?独学の陶芸は人間国宝
2022-10-09
【探究ネタ】「義淵」日本の宗教に携われた人々
2022-05-25
【探究ネタ】「叡尊」日本の宗教に携われた人々
2022-05-19
広告コーナー
いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により
運営させていただいております
皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます
いらすとすてーしょん検索コーナー
いらすとすてーしょん検索コーナー
いらすとすてーしょん検索コーナー
新着偉人(It's New)
新たに公開のイラストポートレートをご覧ください
【文学の部屋|大高ひさを】昭和時代編.222New!!
2026-02-06
1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓
2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です
2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします